他人と生きるための社会学キーワード|第2回(第4期)|梨と二十世紀──「正解」の共同体を越えてコミュニケーションするということ|西村大志
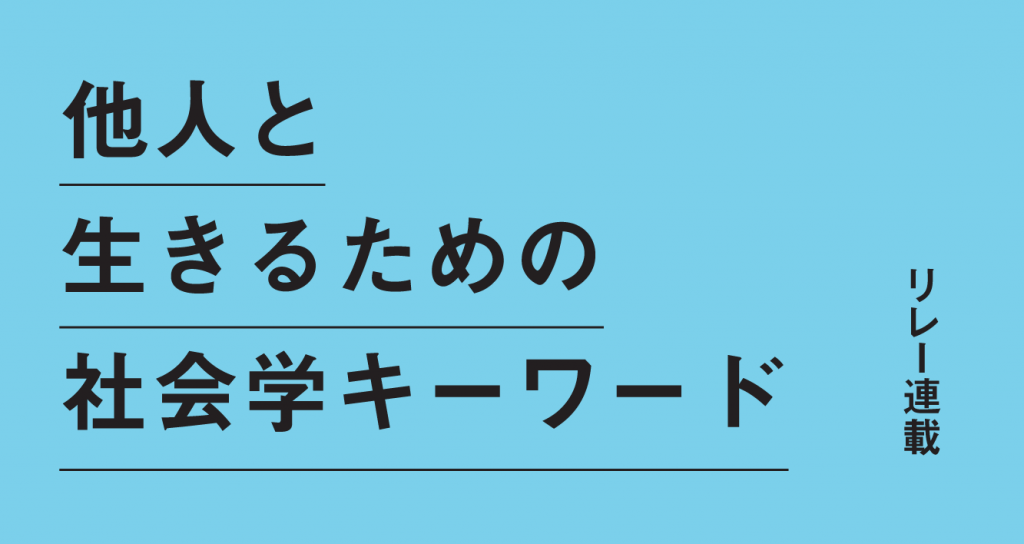
梨と二十世紀
「正解」の共同体を越えてコミュニケーションするということ
西村大志
気分転換に、つい果物事典を開いてしまう。そんな果物好きの私が、梨を見かけると思い出すことがある。小学校4年生のときの担任とのエピソードである。それは、「二十世紀梨は、いつの梨なの?」という奇妙な会話とともに思い出される。当時は1982年、まだ20世紀であった。
担任はおそらく40代後半だった思う。髪型をいつもリーゼントにしており、つねに緑っぽい上下のジャージを着ていた。体育の好きな先生で、なんだかんだと授業を体育に振り替えてしまうので、教室に座っているのが苦手な子どもたちに人気があった。
教員としてもっともらしいことを話すのが嫌いだったようで、クラスの生徒全員に古い歌謡曲がたくさん掲載された小さな冊子を配り、朝礼がわりにみんなで合唱することになっていた。「銀色の道」(1966年)は、そのリーゼントの先生のイチ推しだった。
(「銀色の道」の歌詞はこちらをご覧ください)
先生は「説教するより、歌のほうがいい」とよく言っていた。間接的に道徳を説こうとしていたのだろうか。その小学校の正面には大きな児童養護施設があったりして、家庭環境に恵まれない子どもが多く通っていた。「君のために言っている」的な教員にありがちな表現はおためごかしと感じ、「やればできる」と言われれば、やるまえにすでに差があるじゃないか、と考えているような子どもが多かった。そんな子どもの雰囲気を先生は察知し、「教育的」な言葉の限界を感じていたのかもしれない。
そんなある日、リーゼントの先生は「いまは19世紀や」と言いはじめた。1982年のことだから、当時は20世紀だった。なので私は「先生、いまは20世紀とちがいますか。今年は1982年やから、20世紀。せやから二十世紀梨ってあるやないですか」と言い返した。
梨の名前は根拠にならないのだが、幼いころから筋金入りの果物好きの私は、こんなときにもつい果物を持ちだしてしまった。当時は、青梨系の二十世紀と赤梨系の長十郎が梨の代表銘柄で、二十世紀梨の知名度はたいへん高かった。
ちなみに二十世紀梨は、明治時代の1888年から千葉県で開発され、10年の時を経て1898年に初めて実をならせた。雨の多い千葉では育ちにくく、1904年に鳥取県に持ち込まれて、鳥取が代表的産地となっていった。なので、じつは二十世紀梨は、19世紀に「(未来の)20世紀には代表品種になるだろう」と名づけられたものだということである(日本果樹種苗協会ほか『図説 果物の大図鑑』)。
さて、先生はすこし考えて「いまはやっぱり19世紀とちがうか。1982年やねんから19世紀。二十世紀梨なあ。せやなあ。うーん。せや、あの梨は未来の梨っていう意味で二十世紀梨って名前ちゃうか」と答えた。当時はもちろん19世紀ではなかったが、名づけの方向性として先生の「未来の梨」説は、なかば正解であったかもしれない。スマホはなく、ネットにもアクセスできない時代である。書籍が手元になければ、どこまでも会話ですすんでしまう。
「でも先生、何世紀って、こういう数え方になるんですよ」と私は説明した。リーゼントの先生は素直な人だったので「なるほど、やってみよう」と言った。そして先生は、どう計算したのか「あっ、いまは19世紀ちゃうわ。うん、計算してみたらいまは21世紀や」と言いだした。私はさらに言った。
「いまは、絶対20世紀ですって。先生、じゃあ、二十世紀梨はどうなんの?」
先生は言った。「うん。ということは、あれは過去の梨やな。はるか昔の20世紀からある伝統の梨や。せやからうまい」。
そんな落語のような会話が展開されたあと、その日は1982年が19世紀なのか、20世紀なのか、はたまた21世紀なのか、うやむやなまま会話は終わってしまった。
つぎの日、リーゼントの先生は私を呼び出した。先生いわく、
「家に帰ってから世紀について考えたけど、やっぱり、いまが19世紀なのか、20世紀なのか、21世紀なのか、いまだに自信がもてん。おれはいまは昭和57年やと思ってる。それが一番しっくりくるわな。昭和で言うんが。西暦で言うたら1982年。そこまではわかるわ。自信もある。
うーん、20世紀なあ。おれは、世紀の数え方の仕組みがいまだにようわからんから、いまが20世紀だとしっかりと思えん。せやから、そう言いきれん。せやけどな、おれはおまえのほうがわかってるように思う。きっとおまえのほうが正しいやろ。だから、おまえは20世紀やと思といてくれ。おれは、はっきりとわからんから、正しいと保証はできんけど。
おれは、もう何世紀か考えるのやめた。いまは昭和57年でいく。やっぱり昭和がええなあ」
私はそのとき、ひどく先生を尊敬した。先生は「1982年は20世紀だ」と訂正したほうがよかったのかもしれない。しかし、わからないまま表面上だけ訂正するのは、本当には理解しようとしないことでもある。先生は訂正こそしなかったが、まえの日の疑問を持ち越して考え、そしてつぎの日もまたそれについて、ひとりの生徒とコミュニケーションしようとしたのだ。
多くの場合、教室内では1982年が20世紀であり、2024年が21世紀であるという「正解」が優先される。1982年は20世紀であるらしいとなった時点で、多くの先生はリーゼントの先生と違い、安易に訂正したり、言い間違えたことにして発言をごまかそうとすることもあるだろう。ひどい場合は、自分の間違いを正解として押しつけたりもする。さすがに、1982年が20世紀でないと強弁することは難しいが、正解の定めがたい問いや、正解がいくつもありうるものに関しては、そのようなことがしばしばおこなわれている。教室内には多くの場合、ひとつの「正解」があり、それは教員によってコントロールされている。クラスとはそういう「正解」を共有する共同体であることは多い。
そんなとき、教員も生徒も多くの場合は十分に考えず、「記憶」で処理してしまうことも起きてしまう。ひとつの「正解」を記憶すれば、手間もはぶけ、反応も早い。記憶が思考の省略につながることは多い。しかし、ある共同体での「正解」は、異なった共同体では「正解」でなかったりもする。共同体にいることが当然と考えると、そんなことは忘れられがちだ。
教員のなかには、自分の担当するクラスを特殊な共同体として運営し、自分が語ることを正しいこととし、教室内の児童を一色に染めあげようとすることに熱心な者もいる。そして、そのように共同体を運営するほうが、教員は児童をコントロールしやすい。その共同体の「正解」に異議がとなえられないほど同調圧力をつよめる場合もあり、奇妙なことが「正解」とされつづけている共同体も発生する。共同体になじめない者だけでなく、独自なやり方で「正解」を探求したい者などにとっても、そこへ取り込まれることはかなりの苦痛である。
リーゼントの先生は、先生を頂点とするひとつの共同体に生徒を入れようとせず、私が別の背景をもちつつ別の知を構成することを認めていた。さらに、その知のあり方とどういう距離をとろうとするのかについてさえ、ていねいにコミュニケーションしようとしたのである。
柄谷行人の『探究Ⅰ』を参考に考えてみよう。この書籍のなかで、柄谷は「語る―聞く」「教える―学ぶ」のふたつの関係を設定している。前者の「語る―聞く」は、同一の共同体内を前提として、規則や言語があらかじめ共有されているなかで生じるという。
これを学校にあてはめて考えてみよう。通常の学校あるいは教室というものは、「語る―聞く」になりやすい。そして、児童・生徒は、「語る」側の内容が少々おかしいと感じても、「聞く」ふりをする。あるいは、共同体内の「正解」を察知し、それをもとに動こうとする。そんななかで、先生の「語り」を促進する質問が「いい質問」とされる。「語り」を停滞させるのは「悪い質問」であり、場合によっては、その質問者自体が「悪い生徒」とされることすらある。そして、先生によって語られたことの妥当性は括弧に入れ、聞くことによって得た知識を、記憶によってできるだけ正確に再現することがテストで求められたりもする。ちゃんと「聞いて」いたんだねと。それが得意な者が、いわゆる「ものわかりのよい」人であり、さらにそれが「賢さ」の指標として用いられることすらある。
一方、柄谷によると後者の「教える―学ぶ」は、異なる共同体に属する者のあいだでおこなわれる。ここでは、あらかじめ規則や言語が共有されていない。ここでは、コミュニケーションをおこなうための前提をいろいろと設定するためのコミュニケーションも必要となる。コミュニケーションと同時に、コミュニケーションのルールに関するコミュニケーションをおこなう、という二重のコミュニケーションをおこなわねばならないのである。
もちろん、前者の「語る―聞く」は特定の共同体のルールのもとにおこなわれるので、情報伝達の効率はいい。教科書は、内部での情報伝達の効率を高めるためのすぐれたツールのひとつである。言語および言語使用を共通化し、正解もしくは正しい知識のあり方を設定し、効率化をはかる。しかし、一方で「語る―聞く」の共同体は外部を遮断し、共同体を侵害しそうな本質的な他者を消去する。「語る―聞く」は、共同体内のなかば一方的な情報伝達にすぎないともいえる。そして、柄谷の言うコミュニケーションとは、共同体の違うものとの、コミュニケーションできるかできないかの一か八かの投企なのであり、飛躍でもある。それが、「教える―学ぶ」という真のコミュニケーションなのだ。
そう考えると、リーゼントの先生は私をむりやりひとつの共同体に入れ込むようなことはせず、真のコミュニケーションを試みようとしていたともいえよう。そして、面倒くさい子どもをしっかりと「他者」として尊重し、コミュニケーションの前提となるコミュニケーションのルールについてもていねいに話し合ってくれたのである。
私は、リーゼントの先生とさまざまな知を交換した。先生が教えてくれたのは、けがはさせにくいが恐怖を最大限相手に植えつけることのできる殴り方(小学生編)のような、奇妙な知であった。これがしっかりマスターできると、いじめの対象にならずにすむというのである。子どもが興味をもてば、ぎりぎりのジャンルのことでも懸命に説明しようとする先生と、そのコミュニケーションスタイルを私は好きだった。
のちにリーゼントの先生は校長になったと風の噂に聞いた。歌謡曲を合唱するのをやめて、やむをえず大勢の子どもたちをまえに、訓話のような「語る―聞く」関係になっていったのだろうか。
私の通っていた小学校は、少子化に加え、阪神淡路大震災による地域の急速な人口減少のため、2009年に閉校となった。昭和初期の鉄筋コンクリート造りで風格のあった小学校の建物は撤去され、跡地の片隅に小さな公園が整備されている。その公園の入り口付近には、往時を忍ばせる二宮金次郎の像が置いてある。薪を背負い歩きながら本を読むという、刻苦勉励する像である。その像は現在では持っている本の上半分が折れてなくなってしまっている。それを見ると、さまざまなことを象徴しているような気になることがある。
一方で、いまでも果物屋を通りかかって梨を見るたびに「過去の梨」「未来の梨」の顛末を思い出し、ちょっとほっこりするのである。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
柄谷行人『探究Ⅰ』講談社、1986年(のち講談社学術文庫).
東浩紀『訂正する力』朝日新聞出版、2023年.
日本果樹種苗協会、農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センター監修『図説 果物の大図鑑』マイナビ出版、2016年.
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
西村大志(にしむら・ひろし)
広島大学大学院人間社会科学研究科准教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学、博士(文学)。専門分野:文化社会学、歴史社会学。
主要著作:
『小学校で椅子に座ること』国際日本文化研究センター、2005年
『夜食の文化誌』編著、青弓社、2010年
『映画は社会学する』共編著、法律文化社、2016年
『夜更かしの社会史』共著(近森高明・右田裕規編)、吉川弘文館、2024年
『昭和史講義【戦後文化篇】(下)』共著(筒井清忠編)、筑摩書房、2022年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)


