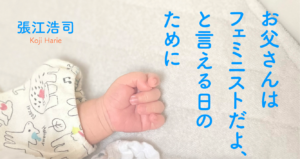いっそ阿賀野でハラペーニョ!|第3回|そこに「暮らし」がたち現れる|高松英昭

第3回
そこに「暮らし」がたち現れる
〝カットマン係長〟の微笑み
市役所の朝はラジオ体操から始まる。始業開始5分前になると、ラジオ体操の軽快な音楽が市役所内に響きわたる。あたりを見まわすと、職員はやおらイスから立ち上がっている。スピーカーから流れる掛け声にあわせて、ラジオ体操を始めるのだ。出勤初日、私はなんだかわからないまま、掛け声に押されるようにラジオ体操をした。
「高松さんもちゃんとラジオ体操していましたね」
係長が微笑みながら、ささやくように話しかけてきた。「夏休みの小学生じゃあるまいし、みんなで体操するのかよ」と私が面食らっていると思って、気づかってくれたようだ。席に戻ると、始業開始を知らせる学校のようなチャイムが鳴った。
地域おこし協力隊として移住者促進のための情報発信がミッションの私は、企画財政課企画係という部署に所属している。企画係は市の総合計画などを担当する部署で、移住に関する事業も担っていた。
「それでは、1000ということにしておきましょうか」
ペルシャ絨毯を売るトルコ商人のように、係長は私に小声で言った。
市役所では年度末になると、次年度の事業目標を立てることになっていて、移住者促進のためのインスタグラムのフォロワー目標数を係長と話し合っていた。そのときのフォロワーは600人ほどだったので、倍近い数値目標になる。
係長はいつも、ささやくように話す。必要なことだけを伝えると、相手の言葉を待つように沈黙する。相手のスマッシュの勢いを殺して何度も打ち返す卓球のカットマンみたいな粘り強いやりとりをするのだ。なんせ、地元出身の係長は吹雪のなか、雪をかき分けながら田んぼ道をすり抜けて、八甲田山の雪中行軍のごとく小学校に通っていたという。雪に埋もれた用水路にズボっと落ちたこともある。その話をしていたときには「下半身が濡れただけですから」と不敵な笑みを浮かべていた。
「フォロワー数は受け身の要素が強いので、800ぐらいでどうでしょう」と私は値切ってみたが、係長はただ微笑んでいる。わずかな沈黙が続く。
「じゃあ、1000ということにしましょうか」
私は沈黙に耐えきれず、事業目標の欄に1000人と書いた。係長は相変わらず微笑んでいる。「高松さん、ノルマじゃなくて、あくまでも目標ですから。それに、1000は区切りがいいですしね」と、協力隊の担当者が係長の隣に立って、沈黙を埋めるようにダメ押しの言葉を注ぐ。担当者も係長といっしょに微笑んでいる。とりあえず、私も微笑むことにした。
私もメキシコのメルカード(市場)でさんざん値切っていたので、数字の交渉にはそれなりの自信があったが、「カットマン係長」の微笑みと沈黙には敵わなかった。こういう交渉は、南国よりも雪国育ちのほうが圧倒的に強い。

お宅はガーデニングショップですか!?
「上司と話したのですが、高松さんは取材経験も豊富なので、自由に活動してもうことにしました。取材先や内容などはお任せします。そのほうが高松さんも動きやすいですよね。前任者が使っていたカメラとiPadが机の引き出しのなかにあるので、それを使ってください。それと、公式インスタグラムの運用規約があるので、読んでおいてくださいね」
着任初日、担当者が朝メシを注文するみたいにあっさりと言った。机の引き出しを開けてみると、小さな一眼デジタルカメラが出てきた。プロ用のカメラと違って、ダイヤルにいろいろな簡単撮影モードが付いている。なんだかよくわからないが、いまさら説明書を読むのも面倒なので、使いながら覚えることにした。
それから、取材で市内のあちこちを動きまわることになるのだが、市役所近くの住宅街に気になる家があった。その家は玄関ポーチにたくさんの鉢花や観葉植物が飾られており、一見するとガーデニングショップと見間違えてしまうほどだった。飾るというより、埋めつくしているというほうが近い。どんな人が住んでいるのだろう、という単純な好奇心で、私は取材の機会をうかがっていた。
「こんにちは。みごとな観葉植物ですね。初めて見たとき、ガーデニングショップだと思ってしまいました」
たまたま通りかかったとき、家主がちょうど観葉植物に水やりをしていたので、私は車を停めて声をかけた。白髪の男性は怪訝そうに私のほうをふり返った。「あなただれ?」という警戒感を全身から漂わせている。
「阿賀野市役所で地域おこし協力隊をしている高松と申します。移住促進のための情報発信を担当してまして、阿賀野市の暮らしについて市民の方にいろいろお話を聞いています。以前からガーデニングショップみたいなお宅が気になっていて、ぜひ、お話をうかがいたいと思いまして。それにしても、みごとなガーデニングですね」
家主から怪訝な表情が薄れていくのが見てとれた。「阿賀野市役所」はキラーワードである。相手の不信感を穿つ破壊力は抜群だ。フリーランス時代の「カメラマンの高松と申します。東京から来ました」とは、信用度が違うのである。やはり、寄らば大樹の陰である。
フリーカメラマン時代は、取材相手の信頼を得るために苦心することも多かった。海外で取材していると、ときにはプレスカード(記者証)の提示を求められることもあるのだが、報道機関などからアサインメント(依頼)がない場合はプレスカードを取得することは難しい。そんなときは運転免許証を見せてしのいだ。
顔写真もちゃんと付いている。日本語が理解できない相手には、それでなんとかなった。たまに勘の鋭い人がいて「ドライバーズ・ライセンスじゃないのか?」と詰問されたこともあったが、「身分証明証です」と言いはって、疑いの目をかわした。嘘ではない。
「ガーデニングは家内の趣味で、植物の世話も家内がしているけど、いまは外出していて午後には戻ると思うから、あらためて来てください。電話番号を教えますので、午後にまた電話してくれませんか」
すっかり警戒心が解けた家主はそう言って、私に自宅の電話番号を教えてくれた。私は市役所に戻って、自分で作って持参した弁当を食べることにした。
定年を機に移住してきた夫妻
市役所職員の昼食は、弁当率が圧倒的に高い。近くに飲食店はあるが、「さあて、今日は何を食べようかな。たまには蕎麦でも手繰るか」と言えるほど選択肢があるわけでもないし、店まではそこそこ歩くのであわただしくもなる。ほとんどの職員は自席で弁当を広げている。
昼休憩になると、役所内は節電のため消灯する。「お昼に市役所に行くと、暗いなかで黙々と昼食を食べてますよね」と、取材先で気の毒そうに言われたことがあった。かつては「裏日本」といわれたような地方なので、冬は黒墨で描いたような曇天が続く。「あれっ、もう夜ですか」というほど所内が暗くなることもある。それでも、弁当箱に詰めた肉団子と梅干しの見分けはつくので問題ないのである。ただ、食後に読書する気にならないほど暗いときは支障を感じるが、そんなときは机に突っ伏して寝ることにした。
午後になって電話すると、オクサンは帰宅しているということだったので、私は再度、お邪魔した。
夫妻は快くリビングに招き入れてくれた。オクサンは地元出身で、ダンナサンの定年退職をきっかけに夫婦で移住してきたという。「強制的に連れてこられたんですよ」と、ダンナサンは笑って言う。初対面のときは気難しそうな印象だったが、冗談好きなフランクな人だった。移住者の体験談は、移住検討者にとって関心の高い情報だから、取材ができるのはラッキーである。
ここでは基幹病院や役所、スーパーマーケットや商店街が徒歩圏内にまとまっているのがよいなど、生活者としての具体的な話を聞いた。東京都心で育ったダンナサンからは「玄関先から山を見ることができ、都会暮らしでは得られない自然環境を楽しんでいる」という、移住者検討者向けの媒体にぴったりのコメントも得ることもできたので、それだけで原稿は書けた。
ただ、夫妻が移住者だったのは、たまたま瓢箪から駒が出たようなことで、やはり私は、ガーデニングショップのように玄関ポーチを鉢花や観葉植物であふれるように飾っていることが気になっていた。育てている植物は100種ほどになるという。オクサンの趣味が高じて、ということなのだが、その情景に、私の頭のなかでは福島県飯館村での体験や多摩川の河川敷に住むホームレスの人が建てた家の光景が重なるように浮かんでいた。

「生活」でなく「暮らし」を取材したい
東京電力福島第一原発事故で全村避難指示が出された飯館村を、友人のライターと取材したことがあった。全村避難に向けて住民説明会が開かれ、村全体が騒然としていた。私たちは村内にある民宿に泊まりながら、「村で見つけた私の宝物」というテーマで、自分の大切している物や風景といっしょに撮影するという写真企画の取材をしていた。
喫茶店を営んでいた女性を購入したばかりの大きな焙煎機とともに撮影し、自動車整備工場を営む男性は新調したばかりの工具とともに写真に収まった。避難を余儀なくされた村への想いを写真で表現しようとした。
村で出会う人たちに声をかけながら取材を続けていると、庭に転がる大きな庭石にロープをかけて動かしている小柄な老人と出会った。「どうしたのですか」と声をかけると、地震で転がった庭石を元の場所に戻しているという。自宅にいつ戻れるかもわからないなかで、老人は小さな体を折り曲げて、大きな庭石をあるべき場所に戻そうとしていた。
東京・多摩川の河川敷に住んでいたホームレスの人の住居は、集めた廃材を利用してブルーシートで周りを囲った簡素な家だった。4畳半ほどの室内に入ると、地面に敷いたべニヤ板をほんの少しずらしてあり、わずかな隙間から小さな白い花が地面から咲いていた。その写真を撮影すると、ホームレス先輩は恥ずかしそうに照れ笑いした。
玄関ポーチを埋めつくすように飾られた鉢花と観葉植物、あるべき場所に戻される庭石、べニヤ板のわずかな隙間に咲く白い小さな花。無関係に思える風景が、私のなかでは確かにつながっていた。
移住検討者向けの情報発信を担当する私は「阿賀野市の暮らしを紹介する」ことを期待されている。買い物がしやすいとか、病院に通いやすいなどの利便性は「生活」に属するもので、「暮らし」とは本質的に違うものだ。
紛争地帯で「暮らし」に触れることはなかった。戦場から逃れた難民キャンプでは、「生き延びる」という合理性のみを追求した「生活」だけがあった。
観葉植物を育てる、転がった庭石を元の場所に戻す、床板代わりのべニヤ板をずらして小さな白い花を大切にする、という利便性や機能性とは離れたところに「暮らし」はある。「暮らし」を「個人的なこだわり」と言い換えてもいい。
「個人的なこだわり」は「暮らし」を実体化し、観葉植物や庭石、小さな白い花となって現れる。難民キャンプではプラスチック製のオレンジ色の皿が機械的に配られ、具がわずかに入ったスープが盛られる。皿の絵柄などに「こだわり」はない。食事を効率よく配給する機能性だけが求められていた。
観葉植物が玄関ポーチにあふれんばかりに飾られている家を見て、私はそこに「暮らし」を感じた。これは感覚的なもので、取材企画書では表現できない。「そこに暮らしがあるんですよ」と言っても、「みんな暮らしてますよ」と、担当部署のなかで一蹴されてもおかしくない。ただ、移住検討者は今いる場所では実現できない「個人的なこだわり」を実体化できる場所を求めているに違いない。
たとえ「こだわり」をもつ余裕もなく避難するように移住したとしても、生活のなかに少しずつ「個人的なこだわり」を積み上げていく。それが「暮らし」となり、地域への愛着が芽吹きはじめる。
ホームレスの人たちや原子力発電所の事故で避難を余儀なくされた住民を取材してきた経験が、「暮らし」を考えるきっかけになった。ホームレスの人たちの「家」を強制的に撤去する「追い出し」と呼ばれる場面をたくさん見てきた。そこに「暮らしている人」への配慮はなく、一方的で乱暴に私には思えた。
原子力発電所の事故も同じだ。放射能という目には映らない物質が、多くの人たちの「暮らし」を一方的に奪っていった。
取材先を私に一任してくれた担当部署の理解がなければ、取材できなかったことかもしれない。ただ、インスタグラムを見た係長は「高松さん、あの家は私も気になっていたんですよ」とささやくように言って微笑んだ。

ホームレスの人が住むダンボールハウスで。鉢植えに一輪の花。花瓶にも花が飾られている

オレンジ色の皿を手に食料配給の列に並ぶ難民(アンゴラ共和国)
写真:高松英昭(以上、4点とも)
(つづく)
高松英昭(たかまつ・ひであき)
1970年生まれ。日本農業新聞を経て、2000年からフリーの写真家として活動を始める。食糧援助をテーマに内戦下のアンゴラ、インドでカースト制度に反対する不可触賤民の抗議運動、ホームレスの人々などを取材。2018年に新潟市にUターン。2023年から新潟県阿賀野市で移住者促進のための情報発信を担当する地域おこし協力隊員として活動中。
著書(写真集)に『STREET PEOPLE』(太郎次郎社エディタス)、『Documentary 写真』(共著)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)