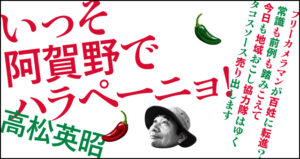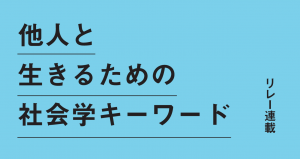雑踏に椅子を置いてみる|第6回|失敗から振り返る「居場所」探し|姫乃たま

第6回
失敗から振り返る「居場所」探し
姫乃たま
これまで当連載では「居場所」をポイントにして、自分の人生を振り返ってきました。しかし読み返してみて思うのは、他者と関わったり、コミュニティに参加したり、そうしたことがどうやってできるようになったのだろうということです。
私たちは生まれた時にそばにいた人をはじめ、さまざまな人との関わりの中でそうしたことを自然に学んでいきます。しかし、自分がまだ人間関係について何も知らない子どもだった頃に、もし教えてもらえる機会があったなら、これは教えておいてほしかったなと思うことを自分の体験からまとめてみました。
ここからは小さかった頃の自分に教えてあげるような気持ちで、「居場所」との関わり方を書いていこうと思います。
「私、コミュ障なんです」
人前で歌ったり喋ったりする仕事をしているので、物怖じしない人だと思われやすいのですが、私は基本的に人見知りです。小さなころは馴染みの親戚の集まりですら怖くて、部屋の物陰にそそくさと隠れる姿が大人たちの笑いを誘ったといいます。
一方で、気に入った絵本やゲームなどがあると、文章にまとめて発表したい気持ちが幼稚園児のころからありました。実際に幼稚園の先生が機会を与えてくれて、クラスで感想文を音読させてもらった記憶もあります。また、お遊戯会などではほかの子たちのようにうまく踊れなくても、平気で舞台に立っていられる妙な図太さもありました。
いまもこうして文章を書いて生活しながら、とても上手とはいえない歌と踊りを舞台で披露していますが、こうしてふり返ってみると、やっていることがあんまり変わらないですね。
おそらく私は子どものころから、大人数の前で何かをするのは平気なタイプだったのでしょう。観客がたくさんいれば、全員に喜ばれることはそもそも不可能です。そのことがかえって気楽だったのだと思います。誰かはすごく好きになってくれるかもしれないし、誰かはふうんと受け流すかもしれません。悲しいけれど誰かには嫌われるかも。それでいいのです。でも私のなかで1対1や少人数の人間関係は、そうはいきません。
いっしょに過ごす以上、相手に楽しんでもらいたいし、少しでも嫌な思いをしてほしくない。なぜか人づきあいにそうした過剰なプレッシャーを感じていて、でも当然最初からコミュニケーションがうまいわけではないので、もともとの人見知りもあり、人とかかわるのが苦手でした。みんなの前で感想文の音読はするのに、あとから個人的に感想をもらってもうまく喋れないというアンバランスな人間だったのです。
いまでも心から感謝している出来事があって、そのときの私はもう高校生くらいだったのですが、けっこうはっきり「コミュ障なんです」と自己紹介してしまう癖がありました。私としては「コミュニケーションが苦手なので大目に見てください」という気持ちだったのですが、当時の担当編集者が「それはよくないよ」と注意してくれたのです。たしかに「コミュ障です」と言ったほうは気持ちが楽になるけれど、言われたほうは「この人は自分と話す気がないのかな?」と思ったり、気をつかったりするしかないわけで、いいことがありません。いま思い出しても恥ずかしい。私は自分本位で本当に「コミュ障」だったのです。
大人になってからときどき、特別仲がいいわけでもない人と笑顔で雑談していると、いつからこんなことができるようになったんだろうと不思議な気持ちになります。相手の人だって、かつては喋るのが苦手な子どもだったかもしれないし、もしかしたらとんでもない怒りん坊だったかもしれません。喋ってる途中で急に走りだしていなくなるような子だったかも。みんないつかは子どもで、ある程度奔放だったはずなのに、いつの間にか相手を傷つけないように気をつけながら雑談なんてするようになるんだから、面白いなあと思います。世間話や雑談って、会話の内容が薄い瞬間もあるかもしれないけれど、私にとっては和やかに笑ってあたりさわりのない会話をできることが、いまでも新鮮にすごいことだと感じます。
いったいどうして、そんなふうにコミュニケーションをとれるようになったのか、過去の苦い思い出や失敗をふり返って考えてみました。
「みんな仲良く」は無理
小学校中学年くらいのころだったと思うのですが、仲のいい同級生の女の子がクラスの男の子たちに嫌われていました。複数人の男の子たちから避けられているような感じで、しばらく観察していると、中心人物になっている人気者の男の子が彼女を嫌いなようで、彼を取り巻いている男の子たちは、その雰囲気に流されてなんとなく同じような態度で接している様子が見えてきました。
私は彼女のことが好きだったので、どうして明確なきっかけもなく嫌われるのか意味がわからなくて、中心人物の男の子と話すきっかけがあったときに理由を尋ねてみたのです。
このときの光景をよく覚えているのは、はぐらかされるかと思いきや、いつもお調子者な彼が、うつむいて真剣に理由と言葉を考え込んでくれたのが意外だったからでしょう。
「⋯⋯なんかじめじめしてるから」
それが彼の答えでした。
私はハッとした瞬間、彼のその感覚がものすごくわかってしまって、当時はどういう言葉で解釈したのか思い出せませんが、つまり「生理的に無理なんだ!」と、とてもびっくりした覚えがあります。
大人は子どもに「みんな仲良く」と口うるさく言うし、子どもだって努力しているけれど、それは無理なことなのだと、そのときに知りました。とくに小学校のような家が近くて同じ年齢という理由だけでひとつの場所に集められるような場所では、いろんな人がいるのだから、全員のことを好きになれなくたってしかたありません。
私は対話を重要だと考えています。相手に自分の気持ちを主張する権利は誰にでもあるし、おたがいの意見が割れてしまったとき、落としどころはどこにあるのか探ることも、それをいっしょに探っていく過程も重要だと思っています。でも、対話にもタイミングがあるのではないでしょうか。
彼が周りの男の子を扇動するようなかたちになってしまったことはよくないけれど、だからといって無理にふたりを仲良くさせようとは、そのときには思えませんでした。いきなり「君のことが生理的に苦手です」から始まる対話は、年齢的にも経験値的にも気持ち的にも、タイミングが悪いように思えたからです。露骨に無視するのはもちろん悪いことですが、ときにはしばらく距離と時間をおくことも人間関係に必要なのだと、このことで学んだのです。
コミュニケーションには場数がいる
では、どうやったら対話ができるようになるくらいコミュニケーションの経験値を積み上げていけるのでしょう。これも、とある出来事が私に教えてくれました。
また小学生のころの話なのですが、学校で飼っていたうさぎのお世話を通じて、ふたりの女の子と急速に仲良くなれたことがあります。学校でいっしょにうさぎのお世話をしてから、放課後は門限ぎりぎりまで毎日3人で遊ぶようになりました。何をそんなに話すことがあるのか、毎日毎日、3人でくっついてお喋りをしては笑い転げていました。
そんな日々が続いたある日、片方の女の子が家の用事で放課後に会えなくなってしまいました。それじゃあその日はふたりだけで遊ぼうと、放課後にふたりきりで会ったら、なんと話すことがなんにもないのです。本当に本当になんにもなかったのです。
いつもは、実はもうひとりの女の子が場を取り持ってくれていたのか、それともその3人でいることでふたりのときには起こらない化学反応が生まれていたのか、それはいまでもわかりません。
「え、私たちってこんなに喋ることないんだ。意外、ウケるね〜」
いまだったら、そんな会話もできるかもしれません。でも、当時の私はなんの切り札も持っていませんでした。いつも門限ぎりぎりまで遊んでいるので、なんとなく途中で帰る選択肢も持てず、ひたすらブランコでふたり並んで無言。仲のいい人同士特有の心地いい沈黙、とかではなく、ただの沈黙でした。気まずくもなかったかもしれません。ただ、どうしてこうなっているのか、そのときの私にはわけがわからなかった。
それからは3人で遊んでいても、なんとなくその日のことが心に引っかかってしまって、誰が言いだしたわけでもないのですが、いつしか自然と同じメンバーで遊ぶことはなくなっていきました。
コミュニケーションには場数が必要だと、このことで私は学んだのです。いまだったら、彼女と雑談でもなんでもできるでしょう。でも、当時の私には何もできませんでした。それは私がまだコミュニケーションの場数を踏んでいなかったからです(幼いころに人見知りで母親にくっついてばかりだったこともあり、もしかしたら同級生と比べても経験が浅かったかもしれません)。
コミュニケーションの上手な人は会話が自然なので、もとから上手なように見えます。もちろん天性の人もいるでしょう。でも私の所感だと、お喋りで場を円滑にまわせる人は、場数を踏んでいるし、自分の発言やリアクションをあとからふり返って反省しています。
なかなか自分のお喋りをふり返ることはないかもしれませんが(あとから断片的に思い出して後悔する人は多いと思います。私もそうですが、後悔にはそこまで意味がないかもしれません)、会話ってその場では普通に感じられても、冷静に聞き返してみるともったいないところが多いものです。
たとえば仕事で文章を書いていると、インタビューでは文字起こしといって、自分がインタビューした音声を聞き返して文字に書きだす作業があるのですが、「どうしてこんなこと言っちゃたんだ!」「どうしてこの話をもっと深掘りしなかったんだ⋯⋯」と、後悔と反省の連続です。そのほかにも発声の雰囲気や喋る速度など、不快に感じる部分があるかもしれません。それらを地道に修正していくと、自分が心地よく感じられる、上手で自然なコミュニケーションに近づいていけると思います。
テレビにもよく出演していて、タレントとして活動している友人は、自分が出演した番組を見返して、発言やあいづちの反省を次に活かすと話していました。私は文字起こしだけでも心がもたないので、自分の出演したトークイベントの映像などは絶対に見返しません。売れている彼女と売れていない私には、そうした努力の差があるのです(遠い目)。
そもそも、そこまでして人と喋りたくないという人の気持ちもわかります。私はなにがなんでも誰かとコミュニケーションをとったほうがいいと伝えたいわけではありません。人間関係に疲れているときは、ひとりになれる時間をつくっておやすみすることもとても大事です。おやすみしているあいだにも、ほかの人は経験値を積んでいるのに⋯⋯と焦ることがあるかもしれません。でも誰かがコミュニケーション上手になったからといって、自分がコミュニケーション下手になるわけではないので大丈夫です。
なにかに興味関心を持つ
最後に思い出すのは、大学生のときにインターンで失敗したことです。ほんの数か月で辞めてしまって、それから企業に就職する機会もなく、今日までフリーランスで働いています。どちらの人生がよかったのかはわかりませんが、あのときにインターンを続けていたら、いまとはまったく違う生活が待っていたのは間違いないでしょう。
私がインターンをしていたのは、とある大手企業の女性向け美容サイトです。そこで化粧品やファッションに関する記事を執筆していたのですが、同じライター仕事でも私がそれまで働いていたのは成人向け雑誌や実話誌、漫画誌などで、ジャンルがまったく違いました。
個人的にも流行りの化粧品やファッションにはあまり興味がなく、出社するやいなや、きれいな正社員のお姉さんたちにヘアメイクから靴まで舐めまわすように見られて、どこのブランドのコスメを使っているのか訊かれても、おばあちゃんがくれたなんだかよくわからない口紅だし、下北沢の古着屋で買った服だし、とにかく私はあの場でとんちんかんでした。そして自分がとんちんかんであることを、あんまりわかっていませんでした。
むしろランチタイムにはみんなで同じようなサラダを食べて、結婚指輪はどこのブランドがいいとか、お肌にいいスムージーがどこの店にあるとか、今季の化粧品はここのがいいとか、まあよくも毎日飽きずに同じような話ばかりできるなと思っていました(当時の私に教えてあげたい、それは昼食と雑談を兼ねた編集会議なのだと)。
それで結局なんの面白みも感じられずに、インターンを自分から辞めてしまったのですが、大人になったいま思うのは、何事にもまずは興味関心をもつことが大切だということです。あのころの私は若かった⋯⋯。
美少女ゲームでも電車でも、大人数のアイドルグループでも、興味関心をもって見れば、最初は全部同じように見えていたものが、次第に立体的に見えてきます。興味関心をもつことは、相手とのコミュニケーションを円滑にするだけではなくて、自分の人生も豊かにしてくれるでしょう。
でも、これがけっこう難しいのです。私は質問するのが下手で、それは人見知りとは関係がなくて、ただなんて質問したらいいのかあまり思い浮かばないのです。それはたぶん、興味関心のもち方が下手だからだと思います。人からどれだけ説明されても、脳の中をすべて滑っていくようなテーマもあります。でも大切なのは、せめて興味関心がありますよという態度でいることで、実際にも心を開いておくように心がけています。
そうしてひとつの事柄を知ると、一見まったく関係ないように見えるほかの事柄との結びつきが見えてきて、世界が広がっていきます。これは私にとって高度なことですが、頭のよい人や人生を楽しんでいる人と話していると、きっとそうなんだろうなということが伝わってきます。
* * *
ここまで文章を書いてきて、過去の自分はこの文章が嫌いかもしれないと思いました。
私は長らく双極性障害の治療を続けているのですが、いまよりももっと鬱の症状がひどかったとき、こうした内容のすべてが自分には不可能に思えて悲しかったのです。自分に元気がないときは、人に興味関心をもっている場合ではありません。信じられないかもしれないけど、誰かと話したいなと思える日が来るまで、そっと待っていれば大丈夫。これもただのタイミングの問題です。一番に自分の気持ちを大切にしましょう。人を尊重するコミュニケーションをとるためには、まず最初に自分を尊重する必要があります。
私が思うのは、興味関心をもつことは大切だし、それによって自分自身の価値観に多少の変化が起きると思いますが、無理に好きじゃないものに合わせていく必要はないということです。
あの大手企業に就職していれば違う人生が待っていただろうなとは思うけれど、じゃあ美容サイトで働きつづけていればよかったかのかというと、私はそうは思いません。
コミュニティに参加するために自分を変える必要はないからです(それがなりたい自分であれば別ですが)。あの場ではとんちんかんだった私も、ほかの場に行けば、同じ自分でもとんちんかんではないと受け入れてもらえます。自分が居心地のいい自分でいられるコミュニティにたどり着くことが大切だと思っているのです。
姫乃たま(ひめの・たま)
1993年、東京都生まれ。10年間の地下アイドル活動を経て、2019年にメジャーデビュー。2015年、現役地下アイドルとして地下アイドルの生態をまとめた『潜行~地下アイドルの人に言えない生活』(サイゾー社)を出版。以降、ライブイベントへの出演を中心に文筆業を営んでいる。
著書に『永遠なるものたち』(晶文社)、『職業としての地下アイドル』(朝日新聞出版)、『周縁漫画界 漫画の世界で生きる14人のインタビュー集』(KADOKAWA)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)