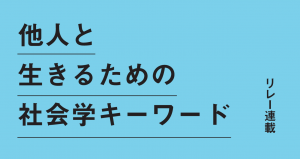お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第7回|抱っこひもとマジョリティ性に振りまわされる|張江浩司
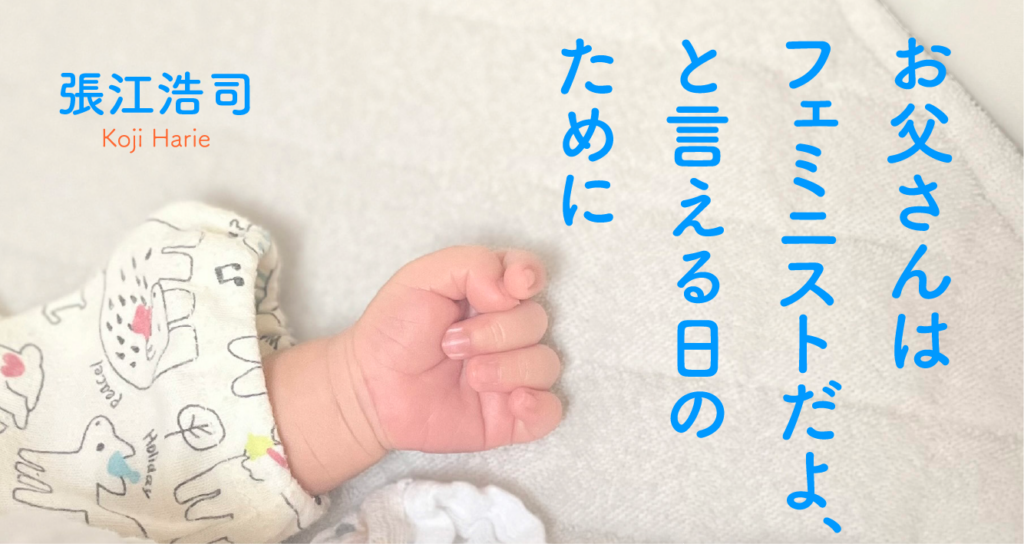
第7回
抱っこひもとマジョリティ性に振りまわされる
張江浩司
変化は急にやって来る
子どもが生後6か月を迎えた。気づいたらもう半年。8月末に生まれたときはまだ夏のまっただなかで、秋冬を超えて暖かな春がやってきた。これで子どもはひととおりの季節を体験したことになる。
⋯⋯ん? まだ半年しか生きてないのに、四季を制覇しちゃうのおかしくないか? たとえば半年後ろ倒しの2月末生まれだったとすると、ギリギリ冬に引っかかったとしても、半年後に秋の気配はまだないはず。これはやはり、夏が帝国主義国家のごとく365日に占める領土をどんどん拡大している結果、秋と冬がギュッと押し込められているということなんだろうか。暑さが苛烈すぎて、夏場は子どもを外で遊ばせることもままならないし、保育園や小学校のプール授業も中止になっていると聞くから、気候変動の気配は育児の領域でもひじょうに色濃い。
ここ最近で、子どもはまた新しい形態に突入したような気がする。これまでは何につけても快/不快の2択しかベースになかったが、より複雑化し、アウトプットのはしばしにニュアンスのようなものを感じとれる。離乳食をなかなか食べてくれないとき、「いまはいらない」「美味しくない」「飽きた」といったような機微を表情、身振り、喃語【ルビ:なんご】の発話で伝えてくる。これは受けとり手である親のリテラシーが向上しているということでもあるだろう。保湿のためにローションとワセリンを塗られるのをとにかく嫌がる子どもなのだが、とくに顔周りを塗られているときはシンプルな不快感だけでなく、「なんでこんなに嫌がっていることがわかってもらえないんだ!」という不条理への絶望をも感じさせる泣きっぷりだ。
機嫌がいいときはゲラゲラとよく笑いもする。体をさすったり頭をなでたりしながら「うー!」とか「ばー!」と言うと、それが子どものなんらかのツボに入ったときに爆笑が起こる。上手くいくと「私はいま、世界で一番面白いのではないか」と恍惚としてしまうくらい笑ってくれるのだが、いまいち再現性がない。
しかし先日、IKEAで買ってきた大きい犬のぬいぐるみを、寝転んでいる子どもの顔めがけて落としてぶつかる直前にキャッチする、ということをやったら「たまんねー!」という感じで笑っていた。その後、何回やってもかならず笑う。もしやこれは「顔にぶつかる!→ぶつからなかった」という「緊張と緩和」が働いているのではないか。落語家の桂枝雀が提唱し、いまやすっかり浸透した笑いの理論が、こんな赤子にも適用されるとは。とすると、1歳の誕生日を待たずして、子どもはナンセンスの世界から論理の世界へ少しずつ歩みだしていることになる。なんとスリリングな大冒険かよ。
きわめつけは、哺乳瓶をみずからの両手でむんずとつかんで飲みはじめた。ただ漫然とチュパチュパしているだけではなく、量が少なくなってきたら、ちゃんと哺乳瓶を傾けて調整している。ただ与えられる存在から、テクニックを駆使してベターな環境を構築しようとする主体へ。前回、「子育ては無意味との戦い」と書いたばかりなのに、このスピード感。変化はじょじょにではなく急にやってくるから、油断できない。意味もなくぐずり続けることもまったく終わったわけではないので、ますます油断できない。
抱っこひもがうまく使えず、妻にあたる
うちの子どもは寝返りがほとんどできておらず、まあそこは個人差があるし、健診では「発達に問題はないですよ」と言われたので心配はしてないのだが、どこかのタイミングで急にクルクル回りだす可能性もあるので、いままでどおりマットの上に転がしておいて家事や仕事をするのも危なくなってきた。抱っこひもを使って対面で抱えながら雑事をこなしたり、原稿を書いたりということはいままでもやってきたが、6か月になったし、首も座ったし、背中におんぶしながらのほうがなにかと楽そうだよねと妻と話し、早速やってみることにした。
取扱説明書を読み、YouTubeで動画を見て、子どもを安全に背負う手順を確認する。抱っこと違って子どもの姿が見えなくなるので、なかなか難しい。もたついているうちに子どもが泣きはじめたので、いったん中断。妻にバトンタッチするとスルスルと背負い、「あ、抱っこより楽だよ」と言いながら洗濯物を干しはじめた。
後日、再度挑戦したけれど、どうにも上手くいかない。そもそも、抱っこひもの長さが私にとっては若干短く、説明書どおりにやろうとすると、子どもを締めつけることになってしまう。見かねた妻がアドバイスをくれるが、やり方自体はわかっているもののそれを実践できないいらだちから、「わかってるよ!」とつい返答が荒くなってしまう。われに返って子どもをおろし、妻に謝罪した。
自分で言うのもなんだが、私は実生活でイライラすることがほとんどない。抱っこひもの何にこんなに反応してしまったんだろうとふり返ってみると、私は「ルールどおりにやったのにできない」ということに慣れていないのではないか。
漫画家の田房永子さんがエッセイ連載「日々のわちゃわちゃ」のなかで、45歳にして運転免許をとった話を書いている(プレジデントオンライン「45歳の漫画家が運転免許を取って初めてわかった『保護者の集まりで誰とも話さず立っている父親たちの境地』」 )。いつも事故に遭わないように注意している歩行者から、加害性の高い自動車側に移ったことで「男性の視点」をかいま見たという。
「男性は女性よりも『あなたは悪いことをやらかしやすい存在である』と教えられる機会が圧倒的に多いと思います。
特に女性に対しては、力の強さや妊娠させる側の性別として『お前は加害性のある側の人間である』『あなたの行動で女性をビビらせる可能性がある』『ビビらせてはいけない』というメッセージを、小さい頃からいろんな形で叩き込まれ、受け取りながら大人になるんじゃないでしょうか。
女性はそういった教えはほとんど受けません。むしろ『被害に遭いやすい性別だから自衛しろ』ということばかり言われます。
つまり、女性に比べて男性は『他人に危害を与える恐れのある車に乗っている状態』に近い感覚を幼い時から持たされやすい性別であると言えるのではないでしょうか」
交通法に従って安全に運転しているぶんには、だれにもとがめられない。万が一、事故が起きたとしても、法律を順守していれば落ち度はない。これまで、性被害にあって警察に駆け込んでもとくに対応してくれるわけでもなく、自衛をうながされるだけだった田房さんにとって、「国家・警察・法律への信頼を持ちながら、同時に見張られる立場になることは、非常に『男性的』」なのだ。
ほかにも目から鱗が落ちまくる論点が盛りだくさんなので、ぜひ全文お読みいただきたいが、つまり法律やルールというのは、規制するにせよ保護するにせよ、その場においてパワー(暴力・権力)を持つものに向けて設定されているということだ。パワーを持つものとは、マジョリティと言い換えられる。
私は日本国籍を持つものとして生まれ、それなりに裕福な両親のもとで育った、五体満足のシスジェンダー・ヘテロセクシュアル(性自認と生まれもった性別が一致している異性愛者)男性だ。日本においてはマジョリティ中のマジョリティといっていいと思う。運転免許を持っていないこととサラリーマンでないことは、多少マジョリティ性からはみ出ているかもしれないが、これは自分で望んだことだし、望んでフリーランスでいられるなんていうことは、マジョリティ性の裏返し以外のなにものでもない。
これは、法律や各種ルール、社会や経済のシステムが想定している層のど真ん中にいるということで、自分の生得的な属性によって不利益をこうむったことは一度もない。「普通」に生きていれば波風が立つこともないし、何かあったらしかるべきところに相談すればいい。街なかの案内板が読めなくて困ることもないし、在留カードを持ち歩く必要もなければ、段差に立ち往生することもなく、満員電車で痴漢にあう心配もない。「ただ自分である」というだけで侮辱されたり危険にさらされたりすることはない。日本国内であればどこにいても基本的に奇異な目で見られることはなく、そこにあるインフラや環境の恩恵を当然のように享受することができる。先のエッセイの最後で田房さんも指摘しているが、自動車をはじめとする工業製品も、男性をユーザーとして設計されている。
これは言うまでもなく、私個人が何かを成した成果などではなく、ただの偶然だ。それは十分に理解しているし、この偶然を自明のこととして振る舞うこと自体が加害や抑圧を生むんだから、注意を払って生活しなければいけないと思っているつもりだった。
しかし実際には、抱っこひもが上手く使えないだけでいらだってしまった。フリーサイズとはいえ、体の大きな男性が使用することをあまり想定しておらず、説明書に書かれた手順をいくら守っても不具合が解消されないものとの遭遇に、簡単に動揺した。マイノリティに「配慮」しながら生きているつもりでも、いざ自分が足の小指の先だけそちら側に規定されそうになったとたんに声を荒げて、妻にあたってしまった。最悪だ。
マジョリティの特権を手放す
以前、俳優の島田桃子さんと話したときに、「戦争とか人種差別には反対してるのに、アンチフェミニストなバンドマンっていっぱいいますよ」と教えてもらった。私も名前は知っているパンクバンドの男性ボーカリストが、海外で起こっている民族浄化に怒り、Black Lives Matterには連帯を示し、同じ口で「でもフェミニズムは女のヒステリー」と笑っていたそうだ。
私もバンドをやっている身として島田さんに申し訳なくなり、頭に血が上ってクラクラしたが、同時にこのパンクスの考えていることも理解できてしまった。
下北沢のライブハウスで、権力に中指を立ててエモーショナルなパフォーマンスをくり広げている。普通の幸せを蹴って東京の片隅でバンドに人生を捧げていて、これで儲かることはないし、将来の展望もない。社会のつまはじき者ではあるが、クソみたいな政治や経済のシステムのせいで起こっている世界中の痛ましい出来事を音楽の力で変えたい。そう思っている彼は、自分はマイノリティに寄り添っていると確信しているはずだし、なんなら社会的なマイノリティだと自認しているだろう。彼にとって戦争や人種差別は、憎み抗うべきものだ。しかし、ここにフェミニズムの視座が導入されると、彼はたちまちマジョリティ性を帯びてしまう。不当な扱いに抗議する側ではなく、加害し抑圧する側に一変してしまう。権力に唾を吐きかけるパンクスとしてのアイデンティティが揺らいでしまうから、彼は「女のヒステリー」と嘲笑して、自身のマジョリティ性をないものとして隠蔽しなければならなかったのだと思う。
私は彼にいっさい共感しないし、「自分の権力性も疑えなくて、何がパンクじゃい!」と思うが、自分のマジョリティ性に振りまわされている点で五十歩百歩だ。
私たちに必要なのは、他者としてのマイノリティを安全圏から眺めることではなく、マジョリティ当事者として、社会のルールや構造にべったり張りついている特権性を逐一認識することだろう。見渡せば、あれにもこれにも。私がマジョリティの特権を享受しているのは私が優秀な人間だからではないのと同じように、このような仕組みがはびこっているのは私が悪い人間だからではない。だが、知ったうえでのうのうと無批判に現状に加担するのであれば、それは恥知らずな人間である。さまざまな困難に直面し、解決しようにも正規ルートではとりあってもらえないような人びとと同じ目線で、いやそれよりも高い解像度で世界を見て、道のガムを剥がすように「たまたまマジョリティである私」が得ている利益を手放さないといけない。
抱っこひもは、自分の体格にあうように手順を少し工夫したら、なんの問題もなくおんぶできるようになった。たとえば夜道で性被害にあわないように、「少しの工夫」を生活のあらゆる場面で強いられている人がいることを、私はちゃんと理解して行動につなげられるだろうか。いや、やるんだよ、とひとりうなずいて、子どものオムツを変える。

人生初映画館。
記念すべき一本は『ウィキッド ふたりの魔女』。
張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)