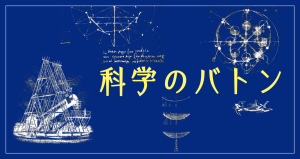本だけ売ってメシが食えるか|第3回|できるだけ「なんでも」選ぶ|小国貴司

第3回
できるだけ「なんでも」選ぶ
うけとめ方が変わったあることば
独立後、変わったことのひとつに、めちゃくちゃ些細なことだが「会社員と自営」の本質的な違いがわかるようになったことがある。
会社員書店員時代、何かの本がよく売れると出版社の営業の人やお客さんに、「いい場所に店がありますよね」とか「この立地はとてもありがたいんです!」とか「売れる場所に出店されましたよね」とか、そのようなことを言われることがあった。
駅ナカのお店や、ターミナル駅の駅ビルなんかは、どう考えても「いい場所」なので、相手としては「ほめことば」として当然のことを言っているわけだが、店長や担当者としては若干モヤモヤするものいいであることも事実だ。
なぜならば、当時は店長や担当者が会社の出店戦略にかかわることはほぼなかった。店舗開発を担当する部隊と上層部が決めてきたお店の間取りを、商品部が棚割りをして、商品選定をおこない(この段階では店長クラスでさえ口をだすことはレアケースだ)、あらかた決まった状態のお店が走りだしてから、ようやく店長と担当者の意思が反映されるようになる。
なので、その立地をほめられても、自分が店舗開発の担当者ならばいざ知らず、現場としてはまったくうれしくはない。それどころか、いくらがんばって商品選定をおこない、日々来店されるお客さんにあわせて棚づくりをしていても「けっきょくお店の立地にすべて収斂されるのか……」という気がして、脱力さえ感じる。もっとナイーブな担当者ならば「立地がいいなら私じゃなくても売上だせるってことね」とすねてしまうこともありうる。
これと似たような現象として「鬼滅現象」のようにひとつのベストセラーの売上のみで「いま売上いいんですよね」みたいに語られる雰囲気も現場のやる気をそぐ。もちろん、立地もベストセラーがあることも、書店としての実力のひとつではあるのだが、売れないときも売れるときも、かわらずおこなっている努力を、だれにでもわかりやすい「理由」だけに落としこむのは、大袈裟にいうと暴力であると思うのだ。
いっぽう、独立してから言われてうれしいことばのひとつに「いい場所にお店を出しましたね」がある。これを言われるとすごくうれしい。
むしろ「いい本置いてありますよね」とか言われると「じゃあ、たくさん買ってくれるんだろうなー?」とか、それに続いて「今日は時間がないから今度ゆっくり来ます」とか言われると「ひょっとして京都流のものいい?」とか、よからぬ感情が(とくに売れていないときは)わくことがあるので、立地をほめられるのは、単純にうれしいのだ。(まぁ、あんまり言われないからうれしいのかもしれないが)。
同じことばを言われても、まったく真逆の感情がわいてくるこの違いは、やはり「自分で決めているかどうか」の違いでもある。自営のばあいは、それにいたるまでにさまざまな意見を聞くことがあっても、最終決定をくだすのは自分自身だ。
立地でいえば、何日も違う時間帯にこれから出店しようとする物件のまわりを歩きまわり、ときには中に入って外を眺め、どういうお店がまわりにあって、どういう人が住んでいるのか観察をする。これは、じつは会社員時代にも、尊敬する上司から言われて、着任前におこなっていたことのひとつだが、自分でお店を経営するにあたってはその先に判断がともなう。
じっさいに、それをおこなっていく過程で「あれ? これは少し違うかな?」と感じる場所もある。そのばあいは、おとなしく引き下がる。そのような紆余曲折をへて、自分の店の場所が決まる。それを褒められてうれしくないわけがない。
もうひとつ、「ナショナルチェーンと自営」の違いもある。
チェーン店は、出店のさいも、開業前からあるていど売上の見える、それなりの立地でなくてはならないのだろう。というよりは、配属される会社員としては、一か八かの賭けをするよりは、ショッピングモールなどのそれなりの費用を払う=来店者数が担保されている物件を狙ってもらったほうがいいに決まっている。
しかし、なけなしのお金を握りしめ、失敗したら(運がよくて)ゼロからのスタートまで追い込まれる創業者はそうはいかない。町のなかに存在する「穴場」としての物件を探しだし、不安と期待を天秤にかけて決断をしなければならないのだ。
実績も信用もない以上、当然ながらショッピングモールなどに入れるわけもなく、来店数が保証された物件などはない。そこが「穴場」だと思ったとしても、開店するまでは賭けに勝ったのか負けたのかはわからない。
ふつうに考えて、論理や常識的な判断では出店できない、と思う。でも、やるしかない。開業前にいくら算盤をはじいてみても、蓋をあけるまではわからないのは、チェーン店も自営も同じではある。しかし、結断する人がひとりである以上、いいわけはできないという点は圧倒的に違う。次はない、という点でも。
その賭けを評価してもらえる、というのは、やはり喜ばしいことなのだ。
気もちよく本を買ってもらうには
古本屋になってから「来てくれたお客さんにどうやって本を買ってもらうか」は、会社員書店員時代よりも、より切実に考えるようになった。これはもちろんすべての売上が自分の生活に直結するというのも大きな理由のひとつだが、じつはそれだけではない気がする。
売上は「客数×客単価」だし、客単価は「買上点数×商品単価」だ。新刊書店員がおそらくいちばんこだわっているのは、いまも「客単価」だと思う。もちろん客数をないがしろにしているわけではない。
ただ僕の会社員時代は、書店がチェーン店だったこともあり、出店する=「それなりの客数は保証されている」立地が多かった。先ほどあげたショッピングモールのなかなどだ。そこでさらに客数を上げるためにうてる施策は、一担当者ではなかなか難しい。つねづね、棚担当者は、買上客数と客単価を増やすための努力をおこなうべきで、店長がやるべき仕事はそれに加えて来店客数を増やすための施策である、と思っていた。
ただし、新刊書店での来店客数と買上客数のギャップは大きい。来店したお客さんが、商品を買っていく割合は、実感としては10人に1人、という感じだ。つまり10人の有効な客数を確保するためには、その10倍も入ってくるお客さんを増やさないといけないというわけだ。
そのギャップを埋めるためには、客数を100人増やすより、やはり買ってくれるお客さんを、2倍にしたほうがてっとり早いに決まっている。そうなると、より買上率の高そうな商品、つまりベストセラーを確保しなければならないのは、当然の帰結といえるだろう。
だが、独立して、ショッピングモールなどの客数が担保された場所ではない場所で古本屋をはじめてみると、考え方が少し変わった。
まず一点目は、客数の圧倒的な違いだ。来店客数が、5人増えたところで、新刊書店時代は、誤差の範囲でしかないが、いまはまったく違う。一日の客数が5人増えたら「今日はお客さん多いな」と思うことだろう。それはやはり立地とお店の規模の違いが大きい。
そして二点目。古本屋に来るお客さんの買上率は、まちがいなく新刊書店よりは高い。10人連続でお客さんが何も買わないで出ていくというのは、新刊書店では気にもとめないだろうが、古本屋は「今日はもうダメだな」と思う。これは規模の小さな新刊書店でも同じかもしれない。
つまりどういうことかというと、お店が小さいぶん、あつかう商品は、よりいっそうお客さんにフィットさせなければならないし、何も買うものがない、ということはそれがあっていない、つまりお客さんのニーズを反映させていない、ということと同義だ。しかも、「わざわざ入ってきてくれたお客さん」に何も買うものがないと思われることほど、商売人として悔しいことはない。
でも、専門書店ではない、うちのような「町の本屋」は、矛盾するようだが、「買わなければならない本屋」にはなってはならない。もっとフランクにフラッと入ってきてもらえる環境をつくらなければならないと思っている。
この「買ってくれないなら来ないでほしい」という思いとまったく矛盾する、「だれでもいいから気軽に入ってきてほしい」という思い。このはざまでするべき努力が、「来てくれたお客さんにどうやって本を買ってもらうか」ということにほかならない。
入ってきてくれたお客さんにどうやったら買ってもらえるか。しかも気もちよく。
自分がよく古本屋に通っていたお客さん時代のことを思い出す。
まずは何も買うものがないお店でむりやり買った1冊の本。これには個人的にはあまりいい思い出がない。もちろんそれがいい本で、あのときあの店に入らなければぜったいに出会わなかった、なんてこともあるだろう。でも、むりやり買わなければいけない、というプレッシャーはできれば味わいたくないものだ。
こういうときは、潔く手ぶらで出ていくのがいい。ぜったいに「買いたいものがいっぱいあるんだけど、いまは本を増やせなくて。また今度来ます。」とか店主に話しかけてはならない。たとえそれが事実だったとしても、そういうときは自分が「過去を変えてはならない未来人」だと思って、だれにも何も影響を与えずに帰ったほうがいい。店主も、そういうときは気づいたとしても無であったほうが自分のためだ。
もし同じ店に月を変えて5回くらい通って、それでも何も買うものがなければ、そこはあなたとは相性がよくない本屋なのかもしれない。万人に気に入られる本屋なんてものはイデアでしかないのだから、そういう店には、本当に気がむいたときだけ行くのが望ましい。
まちがっても「今日は何かあるかもしれない」などと思って定点観測の場にしてはならない。毎日来るのに、いつも手ぶらで帰るお客さん、これほど店にとってストレスフルな存在はない。もちろんお客さんだって、毎日がっかりして帰るのだから、いつしかそれは憎悪に変わることであろう。この世にこれ以上の負の感情を増やしてはならない。
僕としては、そういうお店には、ほんとうに思い出したときに「あ、今日はひまだし行ってみるか」くらい、つまり1年に1回、いや5年に1回行くくらいが適当だと思う。
大切なのは可能性を閉じないこと。「品ぞろえが悪いからぜったいに行かない!」というのは、「なにも品ぞろえだけでそこまで言わなくてもいいじゃん……」と本屋としては(都合がいいかもしれないが)思う。
古本屋とは因果な商売で、どんなに「みんな来てください!」と言っても、どうしても本が好きな人しか入ってこない。したがって品ぞろえは、どんどんそのお客さんたちが買ってくれる本を集めようとするし、そうなると珍しい本を集めたくなってくる。
珍しい本はそれだけ値段も高くなるし、極端なはなし、自分にしか価値を見出せないものや世界に1点しかないものを自分の好きな値段をつけて、もしそれを買ってくれる人がいれば、それは商売として成立しているのだ。
自分しか価値がないと思っているものを、どうやって不特定多数のお客さんに価値を認めてもらえるか、これが古本屋の商売の本質だと思う。だから、どうしてもお客さんをふるいにかけざるをえない。
でも、僕のお店のような存在は、ちょうどそのあいだにいる。「自分の価値観とは関係がないや」という店は、逆をいえばある人には「わたしのための店だ!」になる可能性が高いし、そうなると、わざわざ投資をして家賃をかけて表通りに面して店をかまえる必要はない。
いろいろ書いてきたけれど、もし町の本屋の延長線上に、町の古本屋を置くならば、できるだけどんな本でも置かなければならない。しかし、「なんでも」をできるだけ選ばなくなくてはならない。状態が悪い本よりは、きれいな本を選ぶし、二次流通にむいていない本よりはむいている本を選ぶ。
そして、大事なことだけれど、置いてある本は、どんなになんでも置いておくといっても、お客さんは「店主が選んだ本」と思っていることを忘れてはならない。
小国貴司(おくに・たかし)
1980年生まれ。リブロ店長、本店アシスタント・マネージャーを経て、独立。2017年1月、駒込にて古書とセレクトされた新刊を取り扱う書店「BOOKS青いカバ」を開店。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)