お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第1回|私はいいけど、胎児はどうかな?|張江浩司
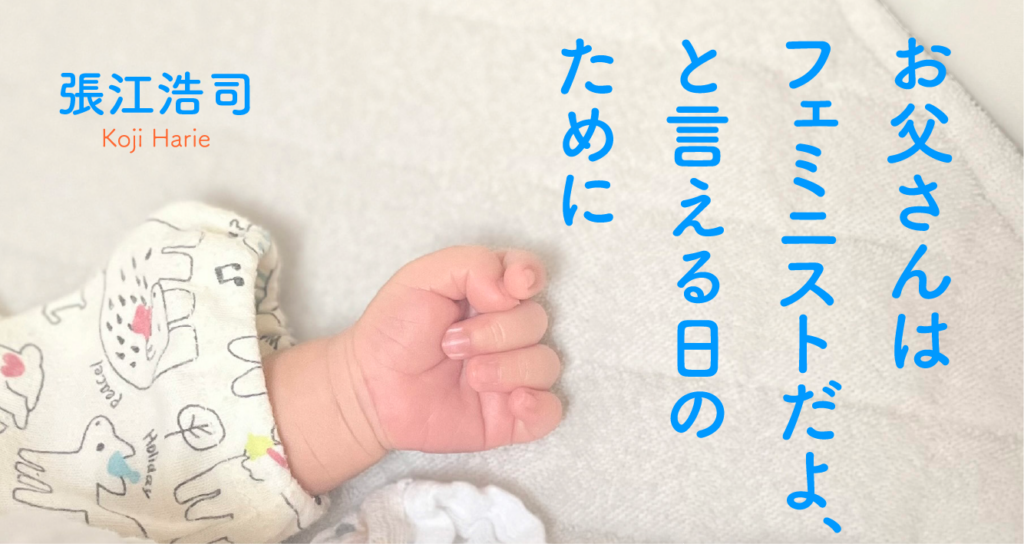
第1回
私はいいけど、胎児はどうかな?
張江浩司
8月27日未明、子どもが産まれた。
いや、この表現だとなんともしっくりこない。これだと子どもがひとりでオートマティックに産道を歩いてやってきたみたいだ。陣痛がはじまってから分娩までの23時間半、天井知らずで強くなる痛みにもんどり打って叫びながら出産を乗りきった妻のすがたを目の当たりにしたいま、「子どもが産まれた」なんて軽々には言えない。
では、あらためて。8月27日未明、妻が子どもを産んだ。
これではあまりに他人事ではないだろうか? これから育児していこうという決意も、妻への感謝も感じられない。
これではどうか。8月27日未明、妻が子どもを産んでくれた。
これも妻が夫のために子どもを産んだようなニュアンスが漂ってきて、いやだ。家父長制をパートナーへの気づかいでシュガーコーティングしたような気持ち悪さがある。
けっきょく、あの凄惨ともいえる出産にまつわるもろもろを的確に表現する一文を、私は見つけることができないでいる。
ライターやったり、バンドやったり、トークイベントやポッドキャストでしゃべったり。「ご職業は?」と問われると「まあ、いろいろっすね
ここ数年でフェミニズム的な視点をもつ映画などの作品を入り口に、世界の見え方が変わったというか、それまでの常識がガラガラと音をたてて崩れるような体験をした私にとって、妻の妊娠・出産は「ハートフルなホームドラマの一場面」を超える出来事になった。
無痛分娩がしたいのに
妻が妊娠していることがわかったのは、年の瀬が押し迫った2023年12月後半。これからかよう病院を選ぶさいに最優先の基準は、「無痛分娩ができること」だった。自宅近くではなかなか見つからず、電車で45分ほどの病院に決めた。万が一に備えて総合病院であることも勘案してのことだ。産婦人科医や助産師のかたがたはどなたも感じが良く、すみずみまで清潔感のある施設で、選択はおおむねまちがっていなかったと思う。
ただ、この病院は「夜間、休日は無痛分娩対応不可」だった。正直、私たちはこの点がいまいちピンときていなかった。
無痛分娩を実施するには麻酔科医の立ち合いが必須で、夜間と休日にはそれができない。なので、出産日を決めてその数日前から入院し、陣痛促進剤を投与することで麻酔科医がいるタイミングで分娩できるようにする、いわゆる計画分娩をおこなうとのこと。そのことで24時間麻酔科医が常駐している病院よりも費用をおさえることができる、という説明だった。
「なるほどなるほど」と納得したし、この説明にうしろ暗いものは何もないのだが、私たちの知識が増えるにしたがって疑問が生じてくる。
初産の場合、陣痛を誘発しても子宮口が開くのに時間がかかることが多い。それを待っているうちに麻酔科医がいない時間になったら、投薬がいったん中止され、背中に麻酔を注入する管を入れられたまま翌日に持ち越される。こうして何日も入院が延長になると、入院費用も馬鹿にならない。麻酔科医がいない時間に陣痛が進んでしまったら、けっきょく普通分娩になるうえに、それまでの麻酔の費用は返ってこない。
二人目以降の出産は相当スムーズになるので、この制限がある計画分娩でもうまくいく可能性は高いが、はじめてである私たちにはメリットが少ないように思えてきた。ネットで情報を集めようにも、無痛分娩の体験談を語っているのは経産婦が大半なことも判断をむずかしくさせる。
思いきって助産師さんに尋ねてみると、「極端に痛みに弱くないなら普通分娩のほうがいいと思います。過ぎてしまえば痛みは忘れますから」とのこたえ。それを聞いて、「私、いける気がする」と普通分娩を決意した妻。「それでも、出産のときは『なんで無痛分娩にしなかったんだ!』って思うんだろうね」と笑っていたが、出産当日に病院に到着した妻は助産師さんに開口一番「今から無痛分娩に変更できませんか
無視される痛み
陣痛開始からおよそ10時間、ここからさらに痛みは強くなる。
「痛み」はひじょうに個人的なものだ。個人の痛みを正確に数値化することはできないし、他人と共有することもできない。逆にいうと「なににどれくらい痛みを感じるか」は、つねに自己形成に深く影響していると思う。
『来る』(中島哲也監督、2018年)というホラー映画がある。その終盤、柴田理恵演じる隻眼の霊媒師はとある人物の手にナイフを突き立て、「痛いですか?」と聞く。感じるはずの痛みがないことにとまどうこの人物にむかって、「生きているということは痛いということです。傷つくし、血も流れます。おわかりですね? あなたはもう
「生きていることは痛いということ」。さまざまな作品でくり返されてきたクリシェではあるけれど、それぐらい「痛み」は人間の生の輪郭をたもつための大きな要素になっているのではないだろうか。そうであれば、その痛みは最大限尊重されなければいけない。それをないものとすることは、個人を否定することにつながる。
しかし、妊娠している女性の痛みは無視される。普通分娩では、どんな激痛でもそれをやわらげる措置がとられることはない。苦痛を訴えても、「がんばりましょう! もうちょっとですよ!」と励まされるだけ。
もちろん、助産師さんたちに悪気なんてものは微塵もない。それは百も承知でも、「赤ちゃんもがんばってますよ! お母さんも!」なんて言われるのを横で聞いているとものすごくモヤモヤしてしまった。胎児が意思をもって「がんばって」いるかはわからないし、もしそうだとしても胎児のがんばりと母体の痛みは別の問題だ。
絶叫するほどの痛みになんの処置もされずただ耐えるしかない異常な状況をして、「普通」分娩と呼んでいることが怖くなってしまった。どう考えても普通じゃない。いままで出産に立ち会ってきた男たちは、自分が愛するパートナーがこんなに苦しんでるのを目の前にして、どう感じてきたんだ。
こんなにテクノロジーが進歩した現代で、妊娠している女性の痛みをやわらげる手段が無痛分娩しかなく、無痛分娩が主流のアメリカやカナダにくらべて、日本では実施されている病院も少なくて制限も多いことに腹が立ってきた。あのとき、なんとしても妻に無痛分娩を勧めておかなかった自分にも腹が立ったし、「母性」や「神秘」ということばでことさら敬ったり、「産む機械」として蔑んだりすることで、この痛みを社会から除外している構造にも腹が立った。
「男は出産の痛みに耐えられない」ということばもよく聞くが、女性は強いからこの痛みに耐えているのではない。誰もとりあってくれないから耐えるしかないのだ。性差による役割分担があるのではなく、「そういうものだから」という理由で訴えを無視されている人たちがいるだけ。ミソジニーの根幹に触れたような気がした。
壮大になっていく怒りでクラクラしながら、夫たる私は妻の腰をさすってお尻を拳で押すことしかできない。助産師さんに「なんとかなりませんか?」と聞いても、「このままがんばってもらうしかないですねー」と返されるばかり(重ねて言いますが、助産師さんの対応に不満はひとつもないです)。自分の圧倒的な役に立たなさのまえに心が折れそうになるが、ナイーブになっている場合ではない。役に立たないなりに、全力で腰をさすって、さすって、右手の中指を擦りむいた。
父、役立たずのスタート
思いかえすと、妊娠5か月目のころ。少し出歩くと、妻のお腹が張って痛みがでるようになった。本人曰く、「ぜんぜん我慢できるくらいの痛み」とのこと。痛くなったらいつでも病院に連絡するように言われているが、この痛みがそれに該当するのかわからない。「大事をとって」というけれど、どれほど大事をとればいいのかがわからない。
念のため病院に電話すると、診察するからいまから来てほしいと言われた。「大事をとって」タクシーで向かい、胎児の様子をモニターすると、「異常なし」。どれくらいの痛みなら病院に連絡するべきか医師に質問すると、「もう一人の体ではないので、少しでも痛かったらすぐ連絡してください」と。
出産当日は逆の意味で、痛みが無視されている。「私はこれを痛いとは思わない」と判断する権利が剥奪されている。自分の身体を自己決定することができない。つねに「私はいいけど、胎児はどうかな?」という、YAZAWA状態だ。
帰りのタクシーで妻と話していると、ドライバーが「お客さん、こないだ私、矢沢を乗せたんですよ」とうれしそうな顔で言った。
子どもが産まれて数日。まだ妻は入院している。毎日面会にいって、顔を見ていると、どんどんどんどん子どもがかわいくなってきている。
それでも、このかわいさでうやむやにならないように、あの日の妻の痛みと私の役に立たなさは、一生覚えておこうと思う。

実家の母からLINEがきた
張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)

