お父さんはフェミニストだよ、と言える日のために|第3回|この衝撃よ、わが子にとっては普通であれ|張江浩司
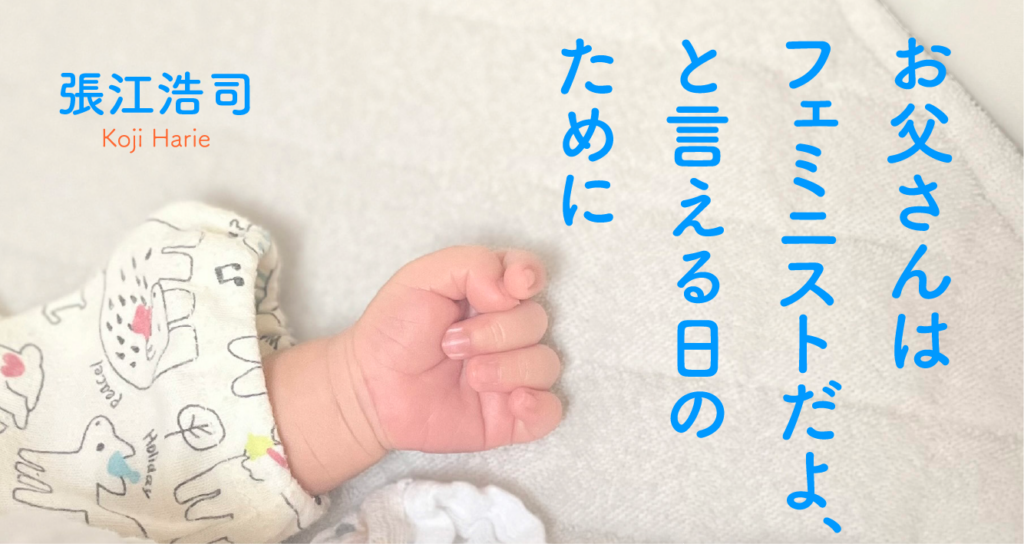
第3回
この衝撃よ、わが子にとっては普通であれ
張江浩司
子どもは世話をするからかわいい
正直、自分はもう少し、子どもに対して冷静なスタンスで接するものだと思っていた。エッセイも書くわけだし、観察者というか、子育てにはコミットしつつ俯瞰した視点から妻と子を見つめることになるんだろうと。しかし、3か月目に突入したいま、その予感は大きく外れた。びっくりするくらいかわいい。前回、「まだ笑わないのもクールでいい」と書いたが、そんなものは目を合わせて「あだー」と笑う子どもの顔を見てないから言えるんであって、それを目の当たりにすると「かわいい、かわいい⋯⋯」しか言葉にならない。かなり真剣に「うちの子どもが一番かわいいんじゃないか」と妻と話しているし、脳内には「♪なんでこんなに可愛いのかよ」というあの演歌の歌い出しがループしつづけている。
ここで、はたと気がつく。あの曲のタイトルは『孫』だ。『子ども』じゃない。初孫のかわいさを素朴に歌って200万枚を超えるヒットを生みだしたシンガーソングライター・大泉逸郎氏であれば、第一子誕生の時点でミュージシャンシップに火がついていておかしくないはず。なぜ、孫が生まれるまで待たなければいけなかったのか。子どもの驚くべきかわいさを率直に歌にしてくれていたら、ぜひ、ひとりカラオケで熱唱したいのに。
ということで、あらためて『孫』を聞き返してみたら、答えは2番の歌詞にありました(ミステリーハンターふうに)。
「仕事いちずで 果たせなかった 親の役割 代わりの孫に 今は返して 今は返して いるところ」
正解は「仕事が忙しかったから」。家庭よりも仕事を優先したことで、とくに乳幼児期の子どもと触れあうひまがなく、孫の世話をすることで子育てを再現している。正確には、この曲は作曲・大泉逸郎、作詞・荒木良治の両氏によるものなので、荒木氏の実体験がベースになっていると思われるが、コンサートでこの曲を歌うと終演後にCDが飛ぶように売れたというから、孫をもつ世代に相当な共感を呼んだのだろう。
おじいちゃんの感慨とはべつに、この歌から浮かび上がってくるのは「子どもは世話をするからかわいい」ということだ。かわいいから世話をするのではない。子育てをやり直すかのように孫の育児にかかわることで、仕事一筋だったかつての父親は愛情をとり戻している。そこにあるのは無条件の愛や大いなる母性ではなく、子育てという複雑な作業をとおした濃密なコミュニケーションの結果としての慈しみだ。
ここで注意したいのは、「子育てという作業が苦痛な人もいる」ということ。子への愛は自動発生するものではないとなれば、実作業でつまずいてしまうと、上手くできない罪悪感や後ろめたさも相まって、素直にかわいいと思えなくなることもあるだろう。授乳時に不快感を覚える「不快性射乳反射」という状態になる人もいるし、一つひとつの作業に向き不向きがあるはずだ。ざっくりと「子育てができない。子どもを愛せない」とするのではなく、状況を解きほぐして原因をつまびらかにし、細かく対処するのは、自分ひとりでは無理だろう。行政を含めた周囲のサポートというか、少なくとも客観的な視点が必須だと思う。
売れっ子ライターじゃなくてよかった
先日、妻が出産後はじめてひとりで外出することになり、4時間ほど子どもとふたりきりになった。ずっと妻とふたりで育児にあたってきたので、たったの4時間とはいえ緊張する。いつもよりもかなり頻繁におむつが濡れていないか確認し、少しでもぐずれば抱きかかえる。泣きだしそうな顔を見ると、助けを求めているような気がする。この小さい命を守れるものは、いま自分しかいない。アドレナリンがドバドバ出て、ヒロイックな気分になった。
この気持ち、家庭を顧みなかったころの大泉氏と荒木氏にも味わわせてあげたいねと思わないでもなかったが、これはこれでヤバい。子どもはまだ言葉をしゃべれないんだから、助けを求めてるかどうかわからない。そもそも、視力は0.01〜0.02程度だそうなので、私を認識しているかどうかもあやしい。にもかかわらず、「この子には自分しかいない!」と思ってしまうのは自分の願望にすぎないし、それが続くと、自分と子どもの境界線が曖昧になってしまいそうだ。
新生児〜乳児期のワンオペ育児は、「言葉が通じない」というハードモードであるがゆえに、親子間の他者性を剥奪してしまう。必死に子どもの心情を想像しているつもりが、自分の願望を投影しているだけ、ということもままあるのではないか。(余談だが、私は子どもにかぎらず、言葉がしゃべれない動物などのキャラクターの心情を大人が代弁するシーンがどうにも気になる。とある日本の映画の予告編を見たら、「タロー(犬の名前)は後悔なんてないんです。なぜだかわかりますか。それは誠実に、懸命に生きてるからです」というセリフがあって、後悔も誠実も懸命も憶測に過ぎなくて気絶しそうになった。
仕事が忙しすぎて育児にかかわれず、いまいち子どもに愛情をもてない父親。ひとりきりの子育てに追われ、自家中毒的に子どもと同一化する母親。ステレオタイプではあるが、仮にこれを日本的な両親とした場合、破綻しないように祖父母を投入するというのは合理的な解決方法に思える。しかし、父親が仕事ばかりに根を詰めず、十分に育児できていれば、そもそも問題はない。
私の場合、調整したわけでもないのに、妻の出産の前週からパタッと仕事の依頼がなくなり、神の采配かのように育休状態になった。フリーランスなので育児休業給付金も出ないから、シンプルに無収入。「このままこの状態が続いたらどうしよう⋯⋯」と仄暗いものが脳裏をかすめないでもないが、それを差し引いても育児に専念できるのはいい。売れっ子ライターじゃなくてよかったと、本心から思う。もちろん、妻が育休を取得していることも大きい。子どもを育てるにあたって、ひじょうにラッキーな環境にいると思う。
最近子どもをもった知り合いのようすをSNSで見かけると、「1か月の育休が今日で終わり。明日から会社に復帰します!」と書いてあったりする。1か月なんて、分娩した人は未だダメージが癒えておらず、そのパートナーは不慣れなケアにてんやわんやしていたら、あっという間に迎えてしまう。そこでタイムアップというのは、育児の負担が増える側からしても、まだ可愛いかどうか感じる余裕もなく育児から切り離される本人からしても、残酷なんじゃないだろうか。せめて丸1年はほしい。
企業で総務人事の仕事をしている友だちに話を聞いたところ、「1年の育休は、有期採用で人員を穴埋めできる。1〜2か月の育休だと、短すぎてそれができないから、ほかの社員が休む人のぶんまで働かざるをえなくなる」とのこと。会社によって事情はそれぞれだろうが、長期育休をとったほうがむしろ職場に負担をかけないことがあるとは。ちゃんとした会社で働いたことがない身としては、目から鱗がボロボロ落ちた。経済面・体力面と育児にはいくつもの懸念事項があるけれど、まずは時間がなければはじまらない、というのが、いまのところの実感である。
精魂こめたド級に面白い説教
時間に余裕のある状態、言ってしまうと「ひま」は重要で、思い返すと私がフェミニズムに興味をもったのも、2019年末に会社を辞めてからだった。それまでは音楽系のプロダクションでマネージャーをやっていて、休みという休みはあまりなかったが、えいやと辞めた瞬間、ドカンと収入が減った反面、無限とも思えるような時間ができた。おりしも世界がコロナ禍に入ったことも拍車をかけ、ぼちぼちとライター業をしながらなんとか食いつなぎ、支出を減らすために友人とルームシェアをはじめ、ダラリと生活した。金はないけど時間はある日々。飲み歩くこともできない時節柄、家で黙々とさまざまなものをインプットするしかない。
それまでもMe Tooムーブメントのようなニュースは追っていたけれど、自分のいる世界とは違うレイヤーにあるものだと思っていたし、いわんや社会的な差別の構造や日本社会においてマジョリティーである自分の権力性に思い至ることもなかった。というか、忙しく働いているなかで、「こういうものだろう」と努めて見過ごすようにしていたように思う。時間があれば、とりあえず酒を飲んでいた。
しかし、たとえば2021年に日本公開されたエメラルド・フェネル監督の映画「プロミシング・ヤング・ウーマン」は、女性というだけで冗談半分に搾取され、未来を奪われてもその被害は「未来ある男性」のために無視されるという構造を、サスペンスフルな脚本と生々しいキャラクター造形で「とんでもなく面白い映画」として描いていて、眉間に180kmの豪速球を投げつけられたような衝撃を受けた。この映画を観た直後に、映画館をはしごしてもう1本観たのだが、ほとんど内容が頭に入ってこなかった。
フェミニズム的なメッセージ性が色濃い作品に対して「説教臭くなくていい」という評価をしばしば目にするし、私も友だちとの会話でなにげなく使ったりしていたが、「プロミシング・ヤング・ウーマン」は「説教くさくて面白い」ところがすごいのだ。精魂こめてド級に面白い説教をしてくれてるんだから、ヘラヘラしてないでちゃんと受けとめなければいけない。こうした作品にどんどん出会って、がんがん蒙が啓かれていった。
これまでなんとなく「おもしれー」と観ていたクエンティン・タランティーノ監督の「デスプルーフ」などに内包されたフェミニズム的な要素にも思いが至るようになる。男性性の象徴たる武装化された車で変質的に追ってくるカート・ラッセルを、最終的に女性たちがボコボコにする映画なんだから、われながらもっと早く気づけよと思う。
「かっけー」と思って聴いていた、アメリカのスリーター・キニーやビキニ・キルなど「riot grrrl」と呼ばれるフェミニストのパンクムーブメントの渦中にいたバンドの聴こえ方も変わってきた。
こうしていると、否が応でも自分が男性中心の構造に安住していたことがわかってくる。じょじょに足元が崩れ落ちて、それまで見えていた世界が組み替えられるようだ。それはある種、爽快さをともなっており、10代のころにハードコアパンクにはじめて触れたときのような価値観の転倒だった。金も肩書きもなくなって、何も持っていないと思っていた自分にそれでもまとわりついていた規範や通念がこそぎ落とされていく。これは身軽だ。
この体験をもって、私にフェミニストと名乗る資格があるとは思っていない。マイナスがゼロに近づいただけだ。まったく勉強不足だし、これまでに男性以外に対して抑圧的な態度をとってきたことも、身に覚えがありすぎる。半年に一度ほど、前職でマネージャーとして担当した女性タレントやアイドルの方々から「フェミニズムとか言ってますけど、私たち張江さんのことがめちゃくちゃ嫌でした」と言われる夢を見て、目が覚めて途方に暮れる。
うちの子どもにはペニスがついていて、それをして「男の子」と言っていいのか、それは大きくなった本人に聞いてみないとわからないが、「男の子」として扱う機会は多い。願わくば、この子にはずっと軽やかでいてほしい。マッチョイズムとかミソジニーとか、私が知らず知らずのうちに背負っていたものと無縁でいてほしい。「プロミシング・ヤング・ウーマン」を観たときに衝撃を受けるのではなく、「普通に面白かった」とちょっと退屈そうに言ってほしい。私が緊張気味に「お父さんはフェミニストだよ」と話しかけたら、「みんなそうでしょ?」と返してほしい。そのためにはどうすればいいのか、とりあえず時間はあるから、考えつづける。

ライター仕事で膝が痛くなる日が来るとは。
張江浩司(はりえ・こうじ)
1985年、北海道函館生まれ。ライター、司会、バンドマン、オルタナティブミュージック史研究者など多岐にわたり活動中。レコードレーベル「ハリエンタル」主宰。
ポッドキャスト「映画雑談」、「オルナタティブミュージックヒストリカルパースペクティヴ」、「しんどいエブリデイのためのソングス」。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)

