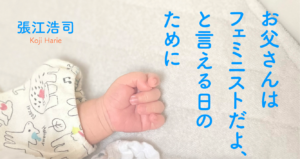雑踏に椅子を置いてみる|第2回|「私のファン」という存在|姫乃たま

第2回
「私のファン」という存在
姫乃たま
初めての私のファン
「どうして地下アイドルになりたかったんですか?」
これまでに一番訊かれた質問です。インタビュアーからも、プライベートで知り合った人からも、よく訊かれました。でも私は地下アイドルになりたかったことはありません。メジャーなアイドルになりたかったわけでもありません。そもそも夢をもったことがありませんでした。
だからいつも「人に誘われたからです」と答えていました。それは本当のことなのですが、それではどうして、軽い気持ちで始めた地下アイドルを10年間も続けて、卒業してから5年が経っても、こんなに真剣に当時をふり返ることができるのか。その理由はやっぱりファンの存在に尽きると思います。
いまでこそ推し活が一般的になって、有名人に限らずあらゆる人(ガソリンスタンドの店員さんとか、学校の先生とか)にもファンがいるのかと思いますが、当時の私にとって、親族でも知り合いでもないのに時間とお金を使って自分を応援してくれるファンの存在は衝撃でした。
私の初めてのファンは、初めてライブをした日に現れました。2009年4月30日のことで、私は高校に通っている16歳の女子高生でした。
舞台に立つように誘ってくれたのは、そのライブを主催していた歌うレースクイーンのお姉さんで(いまなら地下アイドルと呼ばれていると思いますが、このころは地下アイドルという肩書きが当人たちにも浸透していなくて、いろんな表現活動をしているお姉さんたちが限られたライブハウスで歌っていました)、私は当時の私服であったロリータ服を衣装にして、アニメソングを1曲だけカバーして歌って踊りました。
私なりに一生懸命、練習して本番を迎えたけれど、年季の入った客席のファンのおじさんたちのほうがダンスのキレがよくて、やや悔しかったのを覚えています。地下アイドルがブームになるまえからライブハウスに足を運んでいるファンの方々というのは、生まれながらにしてオタクだったとしか思えない、本当に濃いオタクの方々でした(当時はファンをオタクと呼ぶのは御法度でしたが)。
終演後にそんな集団のなかからひょっこりと現れて「これから応援するよ」と声をかけてくれたのが、最初のファンの人でした。頭にタオルを巻いていた覚えがあります。女子高生の私にはずいぶんと年上に感じられましたが、いま思えば30代後半のお兄さんでした。
「これから」もなにも、私はこの日1日だけ思い出づくりのために出演していたので、どうしようと戸惑ったのですが、なんと同時に、「僕が主催しているライブに出演してください」と声をかけてくれた関係者の方も現れたのです。じゃあ、もう少しやってみようかと思ったあの瞬間が、いま思えば人生が大きく変わったときでした。
ファンコミュニティ維持の秘訣
私が出演することになったのは、観客が投票して勝ち負けを決める形式のライブでした。優勝賞金は10万円。高校生には大金です。そのかわり、簡単に優勝することはできなくて、毎月順調に勝ちつづけても、優勝まで最短で半年はかかる仕組みになっていました。
お客さんに配られるのは、ひとり2票。たいていの人が推しの女の子に投票したあと、余ったほうの票を、ライブを観て純粋に「いい」と思った女の子に投票します。それなのでライブに勝つためには、必ず投票してくれる固定のファンと、浮いている票を獲得するためのライブの技術が必要でした。
このライブの技術というのが、歌唱力やダンスの上手さよりも、観客とのコミュニケーションの上手さなのです。歌っているあいだに観客の目を見たり、指を指したり、手を振ったりする。曲間のトーク中に観客からの声に応える(ライブ会場の規模が小さいので、舞台上の女の子に普通に話しかける観客が多かったのです)。そういうことが大事でした。地下アイドルに重要なのは「芸」より「人柄」だったんですね。
よく歌唱力の高い歌手が目を閉じて歌の世界に集中する姿を歌番組なんかで見かけますが、地下アイドルは目を閉じている場合ではありません。観客の目を見なければ。
そういうことはたいていファンの人たちが教えてくれたように思います。私もまたファンの人にオタ芸などを教えてもらうのが面白くて、ライブハウスのフロアでいっしょに遊んでもらっているうちに、彼らが楽しんでくれることは何なのか、自然と考えるようになっていました。そのことに早く気づけたおかげで、最初こそつまずいたものの、一度勝ち進んでからはスムーズに優勝まで駆け上がることができました。
投票制のライブは月1開催なので、翌月までにほかのライブに出演して、新しいファンの人たちと出会います。いろんなライブに出演すればするほど、最初のファンの人を中心にして、応援してくれるファンの人たちが増えていきました。優勝を間近にした投票制ライブでは、会場にしているライブハウスのこれまでの最高動員記録を打ち破るほどの人たちが応援に駆けつけてくれました。もちろん全員が私のファンではありません。同じように駆け出しだったほかの女の子たちのファンも増えてきて、イベント全体が盛り上がっていたのです。
優勝して10万円を手にしたときには、すでにお金には変えられない思い出とファンの存在がありました。ライブに誘ってくれる関係者の人たちも増えていて、私は自然とライブ活動を続けることになります。
投票制ライブで優勝してからすぐ出演したライブに、最初から最後まで毎月欠かさず駆けつけて応援してくれていた、特に熱心な4人のファンが集まってくれました。これまでの数か月間のライブ写真を集めたフォトアルバムとお花を贈ってくれたのです。フォトアルバムの中心には、優勝を聞いた瞬間、感激して涙している私の写真が大きく飾られていました。その写真を見ると、また感動して泣いてしまいます。
「どうしてみんな、こんなに私を応援してくれたの?」
「俺たちは一番に姫乃のことが好きじゃないからだよ」
ファンのうちのひとりが躊躇なく言いました。周りの人もうんうんとうなずいて同意しています。衝撃でした。
そう、これまでの文章だと、私と運命的に出会った一途なファンの人たちが応援しているかのようですが、基本的に地下アイドルのファンというのは、複数、しかもけっこう大人数の地下アイドルを同時に応援しているものなのです。彼らはみんな私を一番に推しているわけではなくて、それぞれに一番好きな地下アイドルをもっていました。だからこそ、私を応援するなかで、ファン同士が競いあったり嫉妬したりすることなく、仲よくコミュニティを維持できていたのです。私を一番に好きじゃないことがファンコミュニティ維持の秘訣だったとは。びっくりしました。
ファンなくして「姫乃たま」なし
こうして最初は手練れの(?)ファンの人たちがつくってくれたコミュニティのなかで活動していたような私ですが、よく共演する女の子や、お世話になっている関係者、そしてファンの人たちが増えてきたこともあって、自分でもみんなに声をかけてライブイベントを主催するようになりました。いつもはカラオケを使ってライブをするのですが、特別にバンドメンバーを集めて、生演奏でワンマンライブを開催する機会にも恵まれました。
自分で出演オファーのメールを書いて、ライブハウスと出演者や事務所の人とやりとりをしながら、イベントのタイトルや告知文、タイムテーブルなどを決めていきます。コンビニのアルバイトくらいしか社会経験がなかったので、基本的には大人たちに助けられつつ、ときに揉まれながらの交渉でした。
無事に主催イベントが終わった翌日は、いつも熱を出すほど大変で緊張もしましたが、自分の好きな人たちに出演してもらって、自分と彼女たちのファンが時間をとって集まってくれることがとてもうれしかったです。いま思えば、周囲の人たちに助けてもらってばかりでしたが、それでも当時の私には、自分で自分の居場所をつくっている実感がありました。
このころ、「アイドル戦国時代」と呼ばれて世間的にもアイドルがブームになると、地下アイドルの世界も活気づいてきました。まず、メジャーになったAKB48系列やももいろクローバーZからファンの人たちが流れてきました。ファンの数が増えればアイドルとの距離は遠くなってしまいますが、小さなライブハウスで活動する地下アイドルであれば、物理的に近距離で応援することができます。
地下アイドルカルチャーが盛り上がってくると、これまでバンドブームの最中には地下アイドルに懐疑的だったライブハウスも場所を貸し出してくれるようになりました。私の活動も地下アイドルとの共演だけでなく、バンドとの共演が増えたり、バンドのゲストボーカルの仕事が入ってくるようになりました。
そうするとバンドのファンだった人が、地下アイドルのファンになったりして、ますます地下アイドル業界にファンが流入するのですが、もともとの地下アイドルのファンのなかには、やっぱり地下アイドルの女の子だけが出演するライブを見たいという人もいます。
ある日、私が男性のバンドばかり出演するライブにひとりだけ地下アイドルとして出演することがあって、さすがにいつもより応援に来てくれるファンも少なく、アウェーな状況にどうしようかと頭を悩ませていたら、最初のファンの人が駆けつけてくれて、ひとりで激しいオタ芸を打ってくれたことがありました。バンドのファンの人たちは、初めて見るオタ芸にびっくり。最終的にはその場にいた人たちが、みんな見よう見まねのオタ芸で応援してくれました。
「芸」より「人柄」を大事にしていた私のライブの技術は、「人柄」より「芸」であるバンドの人たちにとって、けっして高いものではありません。私のライブはファンの人の存在があってようやく完成するものだと、このときに強く思いました。いまでも心のなかでは「ファンの存在があって存在が成立する」というのが地下アイドルの定義のひとつだと思っています。
人が入れ替わってもつくられる場
おかげで活動の幅が広がっていくなか、ファンに支えられているとはいえ、駆け出しのころのような「俺がいないとダメだ」といった感じの危うさは、私から失われていきました。そうすると、駆け出しのころに応援してくれていたファンの人たちは自然と離れていき、ファンの顔ぶれはどんどん変わっていきました。私自身も活動を模索するなかで、表現の仕方が定まっていなかったからでしょう。
いろんな人がいました。「きみは僕の墓場だ(一生応援するという意味)」と言いながら、なんでもなかったかのようにほかの地下アイドルを応援するようになって顔を見せなくなってしまった人とか。そういう人は珍しくなくて、10代の多感な時期をそのように過ごしたことが、自分にどう影響しているのかは、ときどき考えてしまいます。私は私の人生しか歩んでいないので結局はわからないのですが、当時は「大人の人でも思うことって変わるんだな」くらいに思っていたような気がします。
多いときは月に20数本もライブをして、仕事はあったけれど、高校を卒業したら地下アイドルはやめようと思っていました。なんとなく、いつまでもこんなお祭り騒ぎが続くわけないと思っていたからです。相変わらず夢はなかったけど、漠然と将来的には会社(具体的には何も考えていない)に就職しようと思っていました。それが目先の仕事に取り組んでいるうちに時は経ち、大学を卒業したらやめように変わり、ちょうど大学を卒業するあたりでライターとしての仕事も増えてきて、結局は就職活動もせずフリーランスの地下アイドル兼ライターになってしまいました。
それから初めての単行本を出版させていただいたり、CDやレコードを全国流通させていただいたり、出版イベントやリリースイベントで書店やレコードショップにお世話になって、これまでライブハウスで地道に握手をして応援してもらっていたのが、文章や音楽を通じて私のことを知って応援してくれる人たちと出会えるようになりました。
書店やレコードショップでのイベントは、足を運んでくださる人たちにとって、ライブハウスよりも敷居が低いのかもしれません。初めてインストアイベントの舞台に立ったとき、いつも通りファンの人たちが来てくれるのだろうなと思っていたら、見慣れた顔に混じって、これまで会ったことがない観客で店内が埋まっていて、とても驚いたのを覚えています。自分の文章と音楽を通じて、新たな世界が広がっていきました。
(つづく)
姫乃たま(ひめの・たま)
1993年、東京都生まれ。10年間の地下アイドル活動を経て、2019年にメジャーデビュー。2015年、現役地下アイドルとして地下アイドルの生態をまとめた『潜行~地下アイドルの人に言えない生活』(サイゾー社)を出版。以降、ライブイベントへの出演を中心に文筆業を営んでいる。
著書に『永遠なるものたち』(晶文社)、『職業としての地下アイドル』(朝日新聞出版)、『周縁漫画界 漫画の世界で生きる14人のインタビュー集』(KADOKAWA)などがある。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)