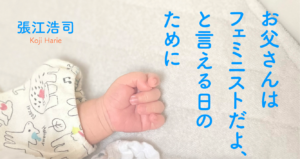こんな授業があったんだ|第49回|詩「初恋」(島崎藤村)を書きかえる〈前編〉|近藤真

詩「初恋」(島崎藤村)を書きかえる 〈前編〉
(中学3年生・2009年)
近藤真
近藤真
初恋 島崎藤村
まだあげ初めし前髪の
林檎のもとに見えしとき
前にさしたる花櫛の
花ある君と思ひけりやさしく白き手をのべて
林檎をわれにあたへしは
薄紅の秋の実に
人こひ初めしはじめなりわがこころなきためいきの
その髪の毛にかかるとき
たのしき恋の盃を
君が情に酌みしかな林檎畠の樹の下に
おのづからなる細道は
誰が踏みそめしかたみぞと
問ひたまふこそこひしけれ(『日本の詩歌』1〈中央公論社〉から)
詩「初恋」を“君”の視点から書きかえる
この授業をデザインさせたものは、私のひっかかりである。この詩をはじめて授業で扱ったのは、まだ20代であった。“われ”が恋慕の情を抱いた対象である“君”は、何を考え、どう“われ”を感じていたのか。この詩では、時間の経過とともに昂じる“われ”の思慕の情は読めても、それに呼応する“君”の心は直接には読めない。──こんなひっかかりをいつのまにか25年間も温めてしまった。
ここでは、詩「初恋」(島崎藤村)を、原詩と同じ七・五調の定型に則って書きかえる活動をとおして〈ことばに立ち止まる力〉を身につけさせようとする。定型は表現の枠組みであり、表現を制約したり束縛したりするものではない。むしろ定型詩という表現形式は、生徒の願いやあこがれといった感情を盛る器となり、短歌と同様「文章では書くことが出来ないことを、テレもせず、心安らかに、表現しうる形式」(飯島正=映画評論家)なのである。
この活動は、もとより自由な詩歌の創作ではない。翻案あるいは再創造とよばれるべきものである。詩のなかで“われ”から呼びかけられている“君”の視点から、“君”になりかわって原詩を再創造する活動である。
詩「初恋」では“われ”=男性の視点で、“われ”の恋の推移が語られてゆく。“われ”に見えたかぎりの思慕やあこがれの対象である、“君”=女性の内面が語られることはない。語られざる“君”のことばをよみがえらせよう。生徒が“君”になりかわって、“君”の恋を追体験するのである。このことによって、原詩「初恋」は、いっそう陰影に富み奥行きを増して読者のまえにたちあらわれるだろう。恋を語るとき、ことばはひときわ光彩を放つ。恋のことばは文学そのものである。
そして、定型詩を書くという高いレベルの課題へのチャレンジによって、生徒のことばの力を引っぱりあげることを企図する。原詩の一つひとつのことばや表現に立ち止まりながら、すなわち原詩との出会いなおしを遂行しながらの再創造は、藤村が謳いあげた詩精神の変奏である。そして原詩「初恋」と生徒が再創造した「初恋」を、四曲一双の屏風として国語教室においたとき、“われ”と“君”との対話的作品が完成する。
同時にこの活動は、相手の身になって感じ考えることのできる想像力、すなわち〈他者感覚〉を育てるための練習でもある。“われ”の恋慕の情に応答する“君”の語りを想像し記述する行為をとおして、この感覚を育てたい。
授業のねらい
詩「初恋」を“君”の立場から定型詩に書きかえる活動をとおして、書かれざる“君”の心情をおしはかり、それが読み手に効果的に伝わるように表現を工夫して書く。また、作品を読みあい、詩の構成や表現の工夫などについて感想や意見を述べあって自分の考えを広げる。
定型詩だから「自由」に書ける
たしかに、生徒にとっては一見むずかしく感じることだろう。ところが七・五調一連四行という表現の枠組みが、かえって生徒の表現意欲を促進した。第一連が書ければ大丈夫。やがてかれらは書くことに没頭していく。定型の軽やかで滑らかな調べに乗ってしまえば、鉛筆の先からことばがつぎつぎに生まれてくる。これは生徒自身にも意外だったようだ。みずから書くことによって七・五調のリズムや呼吸を体感し身体化できれば、自由詩よりもかえって「自由」に詩が書けることに気づく。これが定型の力である。事実、学級の36名すべてが書いたのである。生徒のなかにさまざまな格差や差異をはらんだ公立中学校にあって、このことはなによりも尊い。
虚構だから正直に書ける
「いっそ“われ”の恋人になって思いきり『恋の詩』を作ってみよう!」──これが授業の最初に生徒に発したメッセージである。テキストの一行一語を、“君”はどう受けとったかを想像する。教師は「なぜそう書いたのか」「原詩のどこからそう思うのか」を一人ひとりの学習者に問う。かれらは自分が立ち止まったことばを指さす。これが詩「初恋」を、読者として追体験することではなかろうか。“われ”と“君”との関係が推移する時間を、その当事者になって共有する行為がこの活動である。
中学3年生は、恋愛が大好きだ。しかし、たとえ詩の形式であっても、このテーマで自己を開くには大きな抵抗がある。だからこの虚構のことばに託して、15歳の願いやあこがれが綴られる。一見、虚構の世界に遊んでいながら、かえってそこにその子の正直な気持ちが表現されるという逆説的な現象が生じる。そして、生徒の数だけの相聞の調べがクラスや学年の子どもをつなぐのである。
(つづく)
出典:『中学生のことばの授業』所収、2010年、太郎次郎社エディタス
近藤 真(こんどう・まこと)
1957年、山口県宇部市に生まれ、長崎県北松浦郡で育つ。国語教師として、文学作品の深い読みと創作をとおし生徒がみずからのことばを紡ぐ授業をつくりつづけてきた。著書に『大人のための恋歌の授業』『中学生のことばの授業』『コンピューター綴り方教室』、共著書に『文学作品の読み方・詩の読み方』(以上、小社刊)がある。ほか、『中学校新国語科の授業モデル〈4〉』『情報リテラシー――言葉に立ち止まる国語の授業』(ともに明治図書出版)、『地域で障害者と共生五十年』(小社)などに執筆。〈NHK10min.ボックス 現代文/古文・漢文〉番組委員。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)