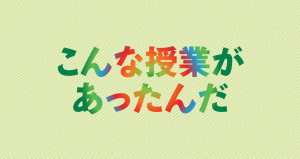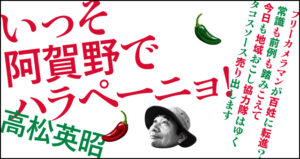保護者の疑問にヤナギサワ事務主幹が答えます。|第2回|防災頭巾が学校指定品⋯⋯?|栁澤靖明
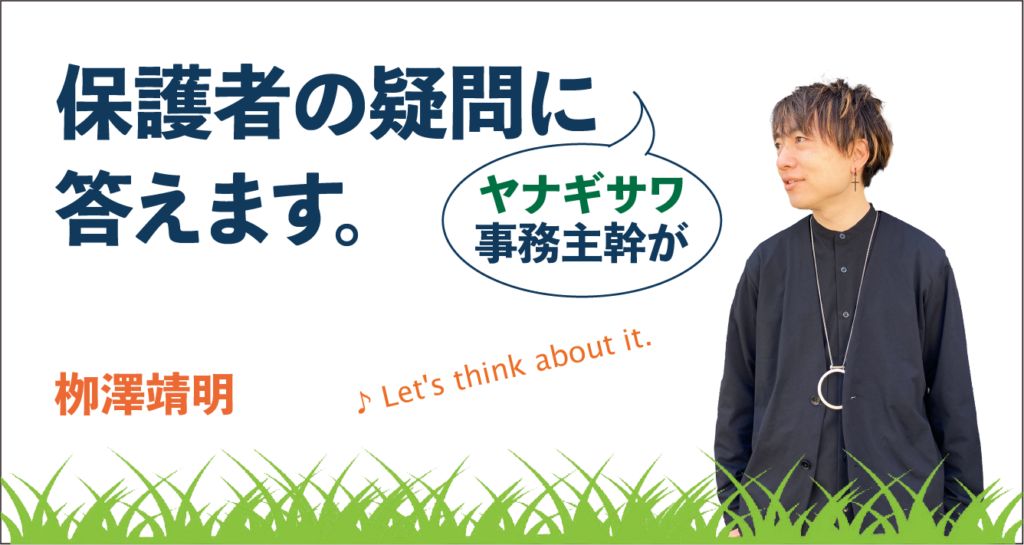
第2回
防災頭巾が学校指定品⋯⋯?
栁澤靖明
地震雷火事親父──子どものころ、よく耳にしたことばですが、最近はあまり聞かなくなったようにも思えます。「親父」がおそろしい時代は終わったのかもしれませんね。このことば、「家父長制」による父親の存在を示しているというもっともらしい説や、自然災害としての台風を表す「大山嵐」から変化したという説もあるそうです(参考:「『地震・雷・火事・親父』の意味や語源とは? もとは『親父』ではなかった?」)。
今回は親父の話⋯⋯ではなく、おもに地震がひき起こす災害への防災備品で有名な(?)防災頭巾について考えていきましょう。
♪ Together──Let’s think about it. ♪
そもそも、なぜ保護者が防災頭巾に疑問をもつの? という読者も多いと思います。まず、防災頭巾と学校のかかわりから説明していきましょう。
じつは、防災頭巾が学校指定品(=『隠れ教育費』)となっている地域もあります。たとえば、関東地方や東海地方で多くみられるようです。そのため、ほかの地域では話題にならないこともあるでしょう。
河北新報の記事によると、防災頭巾は1970年以降、「東海地震への備えで関東や東海を中心に普及した」そうです。文科省調査によれば、2019年3月末時点で「防災頭巾やヘルメットを備蓄している公立学校(中学高校なども含む)は仙台で60%、仙台を除く宮城県は45%」、ほかの東北地方では「青森13%、岩手11%、秋田5%、山形8%、福島18%」と低く、「東京(74%)や静岡市(78%)」は高い普及率であることがわかります。ちなみにその範囲を全国へ広げると、32%とのことです(2021年12月15日「小学校の防災頭巾、効果ある? ヘルメットではだめなの?」)。このように防災頭巾は地震への警戒が生んだ学校指定品ともいえます。
その防災頭巾を入学のタイミングで保護者に買ってもらう学校があるという話から、保護者の疑問が生まれます。新入生学用品セット(算数セットや道具箱など)の一環なんですね。自分の身を守るものだから受益者負担=保護者が負担するという論理で説明されているのでしょう。
防災頭巾の型でみると、頭だけ守る小さいタイプと肩まで守る大きいタイプが主流です。価格は、小さいタイプで2,000円前後、大きいタイプだと3,000円前後くらいでしょうか。人数分公費で購入するのはたいへんですし、保護者負担でも「いざ」に備えるならそれほど高額とは思われないかもしれません。
生地は、アルミ加工が施されているものと布製のものがあります。中綿はポリエステルですが、(公財)日本防炎協会正式認定商品であることがほとんどでしょうし、防炎効果はお墨つきですね。ポリエステルの頑丈さはわかりませんが、衝撃を減らす効果よりも防炎効果を推した商品なのかもしれません。
また、防災頭巾カバー(500円前後)に収納し、平時は防災頭巾を座布団として椅子に装備する場合が多いです。教室のロッカーも広くないので、椅子以外に置いておく場所がないんですよね。苦肉の策、座布団効果を付して「いざ」に備えた保管方法=近くに置いておく方法が編みだされたのかもしれません。そう考えると、椅子につけておくことは、ある意味で理にかなっていると評価できそうです。まぁ、移動教室のときや教科教室制などフリーアドレスには対応できませんけどね。
そして、しつこいですが、中身はポリエステルの綿です。クッション性にもすぐれているし、平時には座布団機能全開で力を発揮しています。しかし、座布団機能全開で使っていると、綿はへたります。「いざ」にじゅうぶんな力が発揮できなくなる恐れもあるため、座布団機能を発揮させていない学校もあるようです。

先の記事にもありましたが、それならヘルメットのほうがよくない? という疑問もあるでしょう。もちろんヘルメットのほうが強靭です。でも、ちょっと値段が張りますね。もうひとつ大きな問題として、やはり置く場所がありません。机のまわりもいっぱいいっぱいで、天板を広げているという話もしましたね(事務主査エディション・第30回「机、広いほうがいいけれど――天板の拡張キット」)。そんななか、それも解決できる商品が生みだされていました。頭巾とメットのあいだ的なコンパクトにたためるキャップです。収納するときは30cm四方&厚さ4cmの形態(ちょっと厚いファイルくらい)で、使うときはジャバラを広げると、キャップ(折りたたみコップみたいな感じ)に変化し、かぶることができます。しかも、衝撃緩衝能力値は頭巾の5倍! でも、お値段は2倍! そんな商品――その名も「でるキャップ」です。
ここまで価格や費用負担者、置く場所に加えて、代替品などを検討しました。じつは、もっと検討が必要な観点があります。それは⋯⋯小学校を卒業すると、防災頭巾もいっしょに卒業してしまうことです。導入率が高いとされている関東地方に勤めているにもかかわらず、中学校で防災頭巾を見たことがありません。
地震王国である日本においても、地域によりその備えに差はあります。そのため、新入生学用品として検討されるかどうかは学校や地域の判断によりますが、小学校卒業後、中学生になったら防災頭巾の不要な身体へ変化する――わけでもありません。しかし、むやみに保護者負担を増やすのも「隠れ教育費」研究室チーフディレクターとして賛成できません。しっかり検討する必要がありますね。
似たような話で、登下校中に頭を守る装備品としての通学帽子があります。わたしの勤務校近隣では小学生だけ黄色い帽子をかぶっています。地域によってはヘルメットをかぶって登校している学校もあるようですが、それでも中学生はノーヘル状態の学校が多いようです。ただでさえ中学生の制服は目立つ色ではありませんから、暗くなると見えにくいです。帰宅時間も小学校より遅くなります。中学生に黄色い帽子がいいのかは別次元の問題として、頭部を守る防具はあったほうがいいでしょう。平時における防災も考えておくべきですね。
さて、「地震大国日本ではすべての児童生徒に防災頭巾を提供し、みずからの身はみずからで守りましょう」という方針で、「防災頭巾無償化法」が成立しないかぎり、全国すべての学校に公費で導入するのは難しいでしょう。購入費用は、独自に予算を組んで設置者負担となるか、学校は必要性だけ訴えて保護者負担をお願いするかの二択――、いや企業負担という可能性もなくはないかもしれません。〇〇協会という企業の連合体が新入生用に防犯ブザーをプレゼントしている自治体もあります。
どんなものを購入するか、だれがその費用負担をするか、平時はどこに置いておくか、そもそも学校指定品とするかどうかなど、さまざまな論点があります。とくに防災頭巾は地域性が強いものです。導入している地域のひと、そうではない地域のひともふくめて、あらためて考えてみませんか。
Let’s think about it.
まずは、パパ友ママ友、そして地域の防災グループで、さらに学校の教職員へ議論の輪が広がったら、「防災頭巾」の新たなかたちがみえてくるかもしれません。それでは、また再来月にお会いしましょう。
栁澤靖明(やなぎさわ・やすあき)
「隠れ教育費」研究室・チーフディレクター。埼玉県の小学校と中学校に事務職員として勤務。「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして現代社会へ情報を発信。研究関心は、家庭の教育費負担・修学支援制度。具体的には、「教育の機会均等と無償性」「子どもの権利」「PTA活動」などを研究している。
おもな著書に『学校事務職員の実務マニュアル』(明治図書)、『学校徴収金は絶対に減らせます。』『事務だよりの教科書』(ともに学事出版)、『本当の学校事務の話をしよう』(太郎次郎社エディタス、日本教育事務学会「学術研究賞」)、共著に『隠れ教育費』(太郎次郎社エディタス、日本教育事務学会「研究奨励賞」)、『教師の自腹』(東洋館出版社)、編著に『学校事務職員の仕事大全』『学校財務がよくわかる本』(ともに学事出版)など。
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)