他人と生きるための社会学キーワード|第8回(第3期)|メディア文化の機能──メディア作品がうながす社会の理解と構築|小林信重
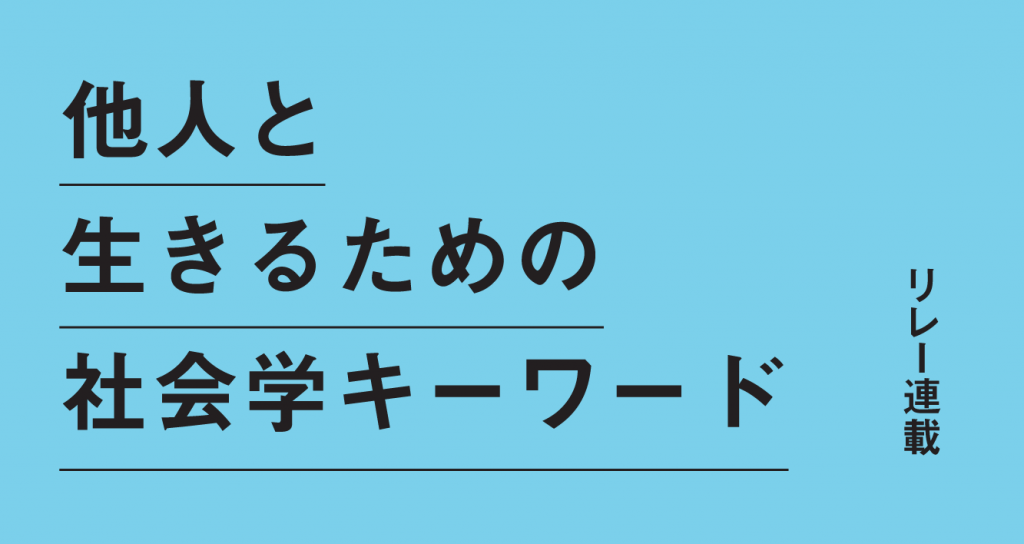
メディア文化の機能
メディア作品がうながす社会の理解と構築
小林信重
人びとを楽しませることを目的として作られてきたマンガやビデオゲームのようなメディア文化は、ときに現実逃避の手段であり、孤立や依存を引き起こしうるものとも考えられてきた。しかし、幾人かの社会学者は、メディア文化が現実社会からの逃避をうながす側面だけでなく、人間が社会を理解しそれを作り上げることを支援する側面にも注目してきた。
たとえば、人びとの文学体験を調査研究したベルナール・ライールは、人びとが現実社会で身につけた考え方を確認したり試したりする機会(自分が登場人物の立場だったらどうするかを考える機会)や、就職・転職、結婚・離婚、家族の誕生・死のような現実のさまざまな状況に適応するために必要な考え方を身につける機会を、文学作品が人びとに与えていることを明らかにした。また、ダニエル・ムリエルとギャリー・クロフォードは、ビデオゲームのプレイヤーに対する調査にもとづいて、ビデオゲームが、現実逃避の手段として機能するだけでなく、私たちが経験したことのない現実の状況や今後も経験することがない状況を体験することを可能にする媒介装置として、他者に対する共感と同一化を促進しうることを明らかにした。
現代のメディア作品では、大ヒット作『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴・集英社)を、現実社会の理解と構築をうながす作品のひとつとして見ることができる。自己の快楽や利益のために人を食べる「鬼」と、自分ではないだれかを守るために命を懸けて鬼を狩る「鬼殺隊」の戦いを描いた本作品では、「鬼の利己性と鬼殺隊の利他性の対立」がくり返し描かれる。たとえば「無限列車」編と呼ばれるエピソードでは、弱者を嫌い鍛錬で得た力を自分のためだけに用いる猗窩座という鬼と、「力を持つ者が、人を傷つけたり私腹を肥やしたりするために自らの力を使うことは許されない」という母親の信念を受け継ぎ、自分の力を弱き人を助けるために用いる鬼殺隊の煉獄杏寿郎との対比が鮮明に描写される。
鬼の始祖である鬼舞辻無惨にとって、自分でないだれかのために命を懸けて戦う鬼殺隊は、「異常者の集まり」と映る。無残と同様に、自分の力を自己利益のためにのみ用いることを当然視する当世風の考えを内面化している読者のなかには、本作品を、自己犠牲を個人に強いる時代遅れの集団主義を賛美する作品としてとらえる者もいるだろう。しかし、人助けを当たりまえと考える主人公の竈門炭治郎や煉獄杏寿郎、鬼殺隊の隊士の利他的な姿を見て、我欲にとらわれた鬼の利己性をむなしいと感じたり、自分の考え方・ふるまい方を省みたりした読者も多かったのではないか。つまり、「鬼の利己性と鬼殺隊の利他性の対立」をくり返し描く『鬼滅の刃』は、私たちが現実の人間や社会のあり方を理解したり、「利他的人間とそれによって構成される利他性に満ちた社会」という人間・社会の理想に近づく方法を考察したりする機会を、私たちに与える役割を果たしたと見ることができる。
さらに『鬼滅の刃』は、社会が人間に与える影響に関する洞察や、善い社会を作るための施策に関する考察をうながす作品ととらえることもできる。本作品では、鬼たちが生まれながらにして利己的であったわけではなく、深く同情せざるをえないほど悲惨な過去の社会的文脈のなかでそのような考え方を身につけたことがしばしば描かれる。たとえば、遊郭に潜む妓夫太郎と堕姫は、「人にされて嫌だったこと、苦しかったことを、人にやって返して取り立てる」「自分が不幸だった分は、幸せな奴から取り立てねぇと取り返せねえ」「言いがかりをつけてくる奴は皆殺してきた」という生き方をしてきた鬼である。しかし、物語が進むなかで、彼らが親からも地域からもさげすまれ差別され身体的・精神的に殺されかけるなかで生き延びるために、このような生き方を選ばざるをえなかったことが明かされる。また、上述した猗窩座についても、命に代えても守りたいと思った人たちを助けられなかったという強い自責の念が、「弱者を嫌い強者を目指す」という彼の価値観を形成したことが語られる。鬼が誕生した経緯を描出する本作品は、「鬼は憎むべきだが、もし自分が同じ環境にあったら、自分も同じような鬼になるかもしれない」という他者への洞察を生み出す。また、「家族や地域からの排除が人を鬼に変える」ことをくり返し描く本作品は、社会から排除されがちな人びとを教育や福祉などによって包摂することが、善い社会を作るうえできわめて重要であることを私たちに思い出させてくれる。
現実社会の理解と構築をうながす作品は、『鬼滅の刃』以外にもいくつかあるが、ここではさらに『タコピーの原罪』(タイザン5・集英社)を取り上げてみたい。本作品は、人間が抱える苦悩の社会的背景や、そのような苦悩を軽減させる方策としてのコミュニーションや物語の重要性を理解させてくれる作品である。
『タコピーの原罪』は、ハッピー星から地球に降り立ったタコピーと、久世しずか、雲母坂まりな、東直樹などの子どもたち、それらの家族、ペットのあいだの関係と、彼女たちの心情を描いた短編マンガである。物語のなかで、タコピーは自分に食事をくれたしずかを幸せにするために、「ハッピーカメラ」「仲直りりぼん」のようなハッピー道具をつぎつぎと使用したり渡したりするが、しずかが体験している壮絶ないじめを解決することができず、何度も悲惨な結末を迎える。タコピーはそのたびにハッピーカメラを使って過去に遡りやり直そうと試みるが、しずかたちとの会話や彼女たちの観察をとおして、しずかたちが拘束されている複雑な人間関係(とりわけ親子の関係や親同士の関係)が、彼女たちの苦悩の原因であることを理解していく。また、読者も、人間の苦悩が家族・学校・地域・友人のような社会のままならない拘束のなかで生み出されることを理解することができる。
さらに、本作品は、人間の苦悩が他者とのコミュニケーションや物語によって軽減しうることを教えてくれる。物語のなかでタコピーは、ハッピー道具をやみくもに使うことではなく、しずかたちの側にいてコミュニケーションすることこそが、彼女たちが抱える苦悩を理解しそれを軽減させうる手段であることを発見する。タコピーと共に読者も、コミュニケーションの重要性に気づくだろうが、さらに慧眼な読者は、『タコピーの原罪』という物語自体が、しずかのように辛い環境にいる現実の子どもたちに向けて書かれていることに気づくことができる。物語のなかで、タコピーは「おはなしがハッピーをうむ」と語る。「おはなし」とはもちろん作中のキャラクター間のコミュニケーションのことであるが、『タコピーの原罪』自体のこともおそらく意味している。また、タコピーは地球の「きみたち」に語りかける。「きみたち」とはもちろん作中のキャラクターのことであるが、この物語の読者のこともおそらく意味している。作品の最後のしずかたちの姿は、過酷な状況にあっても、他者とのコミュニケーションと物語という2つの「おはなし」が救いとなりうること、私たちを幸福にする機会を与えてくれることを、私たちに教えてくれる。
冒頭で引用した社会学者たち(ライール、ムリエル、クロフォード)は、文学、マンガ、ビデオゲームのようなメディア文化・作品が、現実逃避の機会だけでなく、自分の考え方を試す機会や、新しい状況に適応するために必要な考え方を身につける機会、経験したことのない(今後も経験することのない)状況を体験して他者に対する共感と同一化を促進する機会を人びとに提供していることを明らかにしてきた。ライールらと同様、私たちも社会学の見方と方法にもとづいて、私たちが社会を理解しそれを築き上げることをうながすというメディア文化の潜在的な機能に注目することによって、『鬼滅の刃』や『タコピーの原罪』のようなメディア作品が私たちに与えた衝撃を、またそれが人間や社会に与えた多様な影響を、より深く、またより総合的に読み解くことができるようになるだろう。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
ベルナール・ライール『複数的人間――行為のさまざまな原動力』鈴木智之訳、法政大学出版局、2013年
Daniel Muriel and Garry Crawford. Video Games as Culture: Considering the Role and Importance of Video Games in Contemporary Society, Routledge, 2018.
ロバート・キング・マートン『社会理論と社会構造』森東吾・森好夫・金沢実・中島竜太郎訳、みすず書房、1961年
山田真茂留『〈普通〉という希望』青弓社、2009年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
小林信重(こばやし・のぶしげ)
東北学院大学情報学部データサイエンス学科准教授。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(学術)。専門分野:メディア論、文化社会学、ゲームスタディーズ。
主要著作:
『妖怪ウォッチが10倍楽しくなる本――妖怪ウォッチのゲーム・アニメ学』三才ブックス、2015年
『デジタルゲーム研究入門』編著、ミネルヴァ書房、2020年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)


