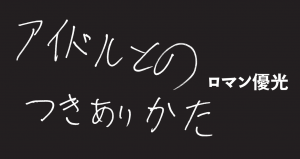他人と生きるための社会学キーワード|第1回|「科学」と「技術」──大事なのはゴールか、プロセスか|岡本智周
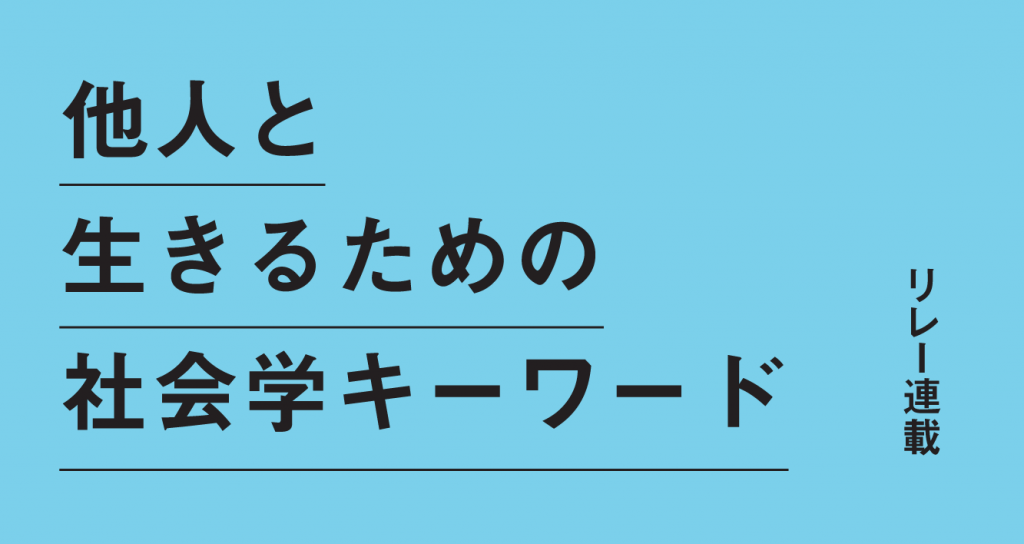
「科学」と「技術」
大事なのはゴールか、プロセスか
岡本智周
近年の日本社会では文系学問への風当たりが強いようで、さまざまな場で、「文系の学問は役に立たない、大学で学んでも先々使えない」といったことがまことしやかに語られるようになった。なかには、「理系の学問に比べて実用性に乏しいので、文系の学部に税金による助成をする必要はないのではないか」といった主張もみられる。
実際に、ほかならぬ文部科学省が2015年6月に示した「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」という通知では、「特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めること」が課題だとされた。文科省サイドはその後、これが直ちに文系学問の軽視につながるものではないという趣旨のメッセージを発したが、少なからぬ大学で現に進行しているのは、文系学問の部局の縮小や再編であり、国立大学法人の統合といった動きである。
しかし考えてみれば、理系の学問のなかでもたとえば数学そのものは実用的・実践的な成果が伴うものではない。他方、法学などは現実に対して即応的で、文系学問のなかでも実利と結びつく性格が強い学問だといえる。実用性の有無によって文系と理系のあいだに線を引くことは、真面目に検討をすればあまり適切なことでもないとわかってくる。
一般に、文系学問と呼ばれるものを正確にいえば人文科学・社会科学であり、理系学問とは自然科学である。人文科学には文学・歴史学・哲学・言語学……といった学問が含まれ、社会科学は法学・政治学・経済学・社会学・人類学……といった学問から構成される。そして自然科学に含まれるのが、物理学・化学・医学・数学・天文学……といった学問である。これらはすべて「科学」であるという点で共通しており、私たちの世界には大別して3つの科学の営みがあることになる。
ここでいう「科学」とは、現象を記述し現象に論理をあてがう作用のことである。またそれによって現象の理論化を図ることである。そのうえで、科学によって得られた理論を別なる状況に適用することが、「技術」と呼ばれる作用である。すべての科学には技術が伴っており、それはどの学問でも変わらない。理系学問にとっての技術はわかりやすいが、文系学問においてもこの意味での技術は存在する。人間についての記述と観察を通して、自分たちがどのような状況にいるのかを表現すること、あるいは、自分たちの環境を整備することがそれである。つまるところ私たちの社会を成り立たせるさまざまな制度づくり、すなわち広く「社会政策」とよばれるものが、文系学問にとっての「技術」の側面である。
そのように見ると、学問が実用性の面から評価されがちであるのは、単純に「科学」の側面以上に「技術」の側面が過剰に着目されるからだとわかる。理系学問においても技術と直結しない部分はやはり軽視されやすく、そのため2018年にノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶佑氏のように、しばしば自然科学者のなかからも、基礎研究への集中投資の必要性がアピールされる。そして、現にある社会制度をつくり支えている文系学問の技術の側面については、あまりに公共的で当たり前な存在であるために、さらに見落とされやすくなる。「役に立つ」学問を求める社会意識はこうしたまなざしと不可分である。
それでは、自然科学と人文・社会科学とのあいだに科学の営みとしての違いはまったくないのかといえば、もちろんそんなことはない。違いは科学的観察の作用にではなく、観察する主体と客体の関係性にある。自然科学においては、観察する者と観察される対象は存在として異なっているが、人文・社会科学においては、両者は同一である。この点が、理系学問と文系学問の性格を分かつポイントだといえる。
どういうことか。たとえば理系学問が水素と酸素の化合や赤血球の機能を研究するとき、それを観察する人間と観察される水素や赤血球は同じ存在ではない。研究者がどれだけ水素や赤血球のことを観察しその動きを理論化したとしても、それによって水素や赤血球の性質や動き方が変わることはない。
一方、文系学問においては、研究対象となるのは研究者と同じ存在である人間である。人間が人間の動きを分析し、人間に伝達するのが人文・社会科学なのである。たとえば社会学者がある社会の平均初婚年齢を調べ、結果を学術的知見として提示したとき、それは調査対象となった社会の人間にも理解されることとなる。その情報は社会構成員が次に結婚に向けて行動する際の判断材料となり、結果としてその社会の平均初婚年齢が変化することが起こり得る。あるいはまた歴史研究の場合も同様である。ある事象に関する新資料が発見され新たな解釈が提示されると、それは現在にまでつながる人間や社会の像を変化させることにもなる。
このように、研究を行うことが対象を変化させ、そのために科学的知見にも修正が重ねられていくプロセスが、人文・社会科学の営みには不可欠となる。英文法で再帰代名詞というものを習うが、それは自身を動詞の対象とする文章で用いられる。それと同じように人文・社会科学では、対象に対する言及がその対象自体に影響を与え、対象の動きにとっての条件にもなるのである。研究者と研究対象とのあいだに再帰的な(reflexive)関わりが生じる点が、自然科学と異なるところとなる。
したがって、自然科学では科学的知見が人間の存在とは別に積み重なり蓄積されていくのに対して、人文・社会科学ではそれが一方向的に蓄積されていくことはない。自然科学がもたらす技術にはゴールの実現を可能にする「目覚ましい成果」があり得るのに対して、人文・社会科学においては科学の営みと人間社会のあり様がお互いに影響を与えあって進展するプロセス自体に価値があることになる。人文・社会科学がもたらす技術はより日常的に社会を支えるものとして存在する。こうした文系学問の特徴が、「役に立たない」ようにみなされがちな理由なのだろう。
しかしながら昨今の日本社会では、行政文書の廃棄や改竄という、人文科学の営みからすれば考えられない行為がきわめて安易に行われるようになった。社会科学の営みそのものである行政調査においても、データの収集や管理の面での不備や、分析手続きの杜撰さが目に余るようになってしまった。文系学問を軽視する社会においては、文系学問がもたらす技術も正常に作用しなくなるのだといえよう。人文・社会科学と社会そのものが相補的に進展するプロセスを重視することは、人間の社会的な生存環境を維持し改善していくうえで、やはり決定的に必要なことなのである。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
室井尚『文系学部解体』KADOKAWA、2015年
隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』星海社、2018年
アンソニー・ギデンズ『社会の構成』門田健一訳、勁草書房、2015年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
岡本智周(おかもと・ともちか)
早稲田大学文学学術院教授。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程修了。博士(文学)。専門分野:教育社会学、共生社会学、歴史社会学、ナショナリズム研究。
主要著作:
『国民史の変貌』日本評論社、2001年
『共生社会とナショナルヒストリー』勁草書房、2013年
『「ゆとり」批判はどうつくられたのか』共著、太郎次郎社エディタス、2014年
『共生の社会学』共編著、太郎次郎社エディタス、2016年
『教育社会学』共編著、ミネルヴァ書房、2018年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)