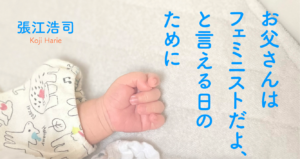他人と生きるための社会学キーワード|第9回(第4期)|幻想のメリトクラシー──学校教育は「教育格差」を埋め合わせればいいのか|津多成輔
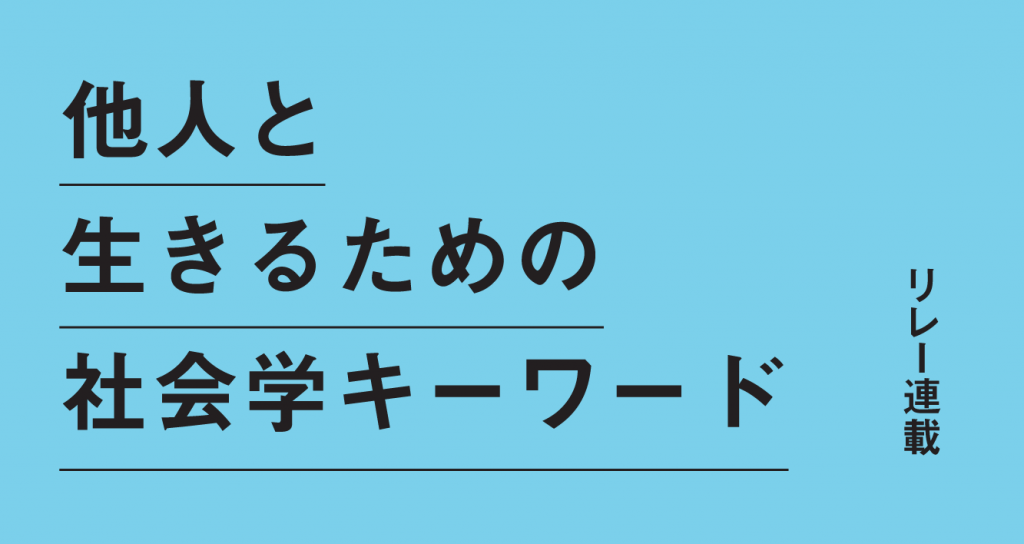
幻想のメリトクラシー
津多成輔
「学歴社会」とされる日本において、大卒者と高卒者の平均生涯賃金の差は6000万円ほどである。「学歴」による収入の差であれば、この差はある程度納得されるのかもしれない。ある県の高校生を対象とした近年の調査結果では、高校生の約8割が「学歴は本人の実力をかなり反映している」と考えているとされる。なるほど、身分によって社会的地位が決まっていた身分社会に比べれば、だれもが努力によってより高い社会的地位に到達できる可能性があると思える近代社会は理想的である。
言うまでもなく、「学歴社会」においてよりよいとされる大学に進学できるかどうかは、受験のための学力が重要になってくる。大学進学だけではない。高校教育が「進学校」「中堅校」「進路多様校」に分かれているように、高校受験(あるいは中学受験、小学校受験かもしれないが)のさいのテストの得点によって、進路が大きく変わるのがいまの日本社会である。高校選択や大学選択を考えるさいに、学力偏差値によって序列化された学校一覧を目にすることも少なくない状況にあっては、それも当然の感覚である。
この受験学力は、児童・生徒の努力によって左右されるというのが、一般的な学校教育現場の認識である。たとえば、私がある県の高校の進路指導担当の教師を主たる対象としておこなった調査では、学業成績をもっとも左右する要因として約半数の教師が「本人の努力」を挙げた一方で、「親による教育」などの保護者に関する項目を挙げた教師は1割程度であった。たしかに、学習指導要領に規定されたカリキュラムに沿って同様の学習内容を履修し、共通一次試験あるいはセンター試験、そして現在の共通テストのように、皆が一律に同じ内容の試験を受ける日本の選抜システムは、平等に機会が開かれているようにも思える。それゆえに、各種の社会調査では、「社会的地位」や「経済的豊かさ」は努力した人や実績をあげた人が多く得ることが望ましいとされる。とくにその傾向が顕著なのは学校教育現場であり、教師の多くが、努力した人が多くを得ることが望ましいと考える傾向にあることが明らかになっている。
他方、昨今は保護者の経済力や文化的資源が子どもの進路を左右することを表現した、「親ガチャ」という言葉が話題になっている。はたして、われわれが平等だと感じている日本の選抜システムは、どれほど「平等」なのだろうか。結論からいえば、本人の努力だけでは乗り越えられない「教育格差」がそこにはある。小学6年生と中学3年生の全員を対象に毎年実施されている全国学力調査におけるテストの平均正答率は、子どもたちを家庭の社会経済的背景(家庭所得、父親学歴、母親学歴を合成した指標)によって4区分した場合に、もっとも低い層の家庭の子どもと、もっとも高い層の家庭の子どもとでは20%以上の開きのある教科がある。この正答率の開きには、本人の努力の結果が反映されていると思われるかもしれない。しかしながら、社会経済的背景がもっとも高い層の子どもがまったく勉強をしていない場合の平均正答率を、もっとも低い層の子どもが毎日3時間以上勉強しても上回ることができていないことが、統計的に示されている。端的に言えば、社会経済的背景によるテストの平均正答率の開きを、努力だけでは挽回できない。
テストで測られる学力だけではない。大学進学率も、家計の所得が1000万円以上と400万円以下のあいだでは約30%の違いがある。この状況は日本だけではなく、世界の大学ランキングで上位に位置づくハーバード大学の学生の3分の2は、所得規模で上位5分の1にあたる家庭の出身であるとされる。このような「教育格差」について、『実力も運のうち──能力主義は正義か?』を著作とする政治哲学者、マイケル・サンデルは、「勝者」が自らの成功を努力と勤勉の結果だとみなすことは、そもそも事実にそぐわず、「敗者」に対して低迷する賃金だけではなく社会的敬意の損失をもたらすと批判している。勉強に一生懸命取り組むことでテストの得点が上がる部分はあるが、その一方で、だれしもが努力によってより高い社会的地位に到達できるとはいえない状況にあるのもまた事実であろう。
それでは、現在の学校教育は「教育格差」を縮小できているのだろうか。先に述べたように、高校を卒業すれば、あるいは高卒認定試験に合格すれば、大学を受験することはだれにでもできる。このように、大学の受験資格がだれにでも開かれている点において、学校教育は形式的には平等である。また、相対的に受験学力が低い子どもたちを対象とした補習授業等の個別の取り組みも、局所的にみれば受験学力が高い子どもたちとのテストの得点の開きを小さくすることに貢献している。他方、テストの点数によって人びとを順位づけることが、学校教育の主たる役割となることは、むしろ「教育格差」を拡げることになっている。たとえば、「進学校」においては成績上位層の子どもたちが、教師から進学に関する情報を多く受けとっていることや、大学入試において受験学力に基づいた選抜を内面化していくことが指摘されている。
そのような状況を含めて考えると、現在の学校教育には人びとのあいだに違いを生みだす機能があるといえるかもしれない。どういうことか。学校教育において、子どもたちの進路はテストや日々の学習、あるいは教師との日常でのやりとりをとおして分かれていく。このように学校教育が資質・能力に応じて子どもたちをそれぞれの社会的地位に結果的に振り分ける機能のことを、社会学の用語では「選抜・配分」という。高卒就職ではなく大学進学、あるいは「よりよい」とされる学校に進学するためには、より高い受験学力が求められるわけだが、現在の学校教育はこの受験学力に象徴されるような単一の指標によって、ある人を優位に、ある人を劣位に格付け、相対的地位をタテに規定する側面がある。
一方で、高校教育が発足した1947年当初の高校教育の理念では、人びとの相対的地位をタテに規定するのではなく、普通科も専門学科も、全日制も定時制も一様に扱われることを原則とする「ヨコ並び」の姿が目指されていた。具体的には、高校教育が戦前の尋常小学校を卒業したのちに進学する旧制中学校のような、一部の高い社会階層のためのものではなく、広く国民一般に開かれた学校にすることが意図されており、希望者を全員入学させることを理想とする方針がとられていた。これに加えて、生徒の通学が容易にできるよう定時制課程の設置や学区制の導入、生徒が自らの進路や適正にあった学科を選択できるように1つの学校に複数の学科を併置することが望ましいとされていた。ここで特筆すべきことは、高校教育の発足時の理念が「ヨコ並び」という言葉に表現されているように、その教育理念にマイケル・サンデルが「社会的敬意の損失」として批判した受験学力に象徴されるような単一の指標によって、人びとの相対的地位をタテに規定することは含意されていないことである。
しかしながら、1956年の学習指導要領の改訂では、高校教育は生徒自身が自らの教育課程を編成できる選択科目制を廃止し、社会からの一定の要請に従って生徒を導くというコース制が導入される。1963年の経済審議会では、近代化による経済成長が目指されるなかで必要な労働力を開発するために「能力主義の徹底」が政策のなかで打ち出される。結果的に、その後の日本経済はさまざまな要因によって当時予期されていた以上の成長を遂げたことにより、受験学力による選抜が正当化されていった。
加えて日本では、職務に必要な能力は企業内訓練によって習得することが一般的であった。このため、その企業内訓練に応えられる潜在能力をもつ者を選別するさいに、採用の基準が、仕事上で必要となる知識・技能・態度などを短期間で習得するために必要となる能力の代理指標として学歴が適合的であったことも事実である。受験勉強では、多くの科目を短期間で学習し、的確に理解し、試験において表現できることが求められており、より効率的にそれらを遂行できたものが結果的に高い学歴を得ているとされる。以降、現在に至るまで、基本的には受験学力によって社会的地位が規定されてきたことは、ここまで触れてきたとおりである。
それでは、学校教育に携わる人びとはどのように「教育格差」にたち向かえばいいのだろうか。受験学力の獲得において、保護者の学歴や経済力、あるいは地域や持って生まれた個々人の特性などによって相対的に劣位な立場におかれる子どもたちは一定数存在する。その子どもたちが受験学力を身につけるような教育をすれば、その能力の競い合いにおいてはいくらか平等に近づくかもしれない。しかしながら、その過程に位置づけられた学びは第一義的に競争の道具にすぎない(「学校の社会的機能──知識は他人と共有するからこそ意味がある」を読んでみてほしい)。
だとすれば、受験学力によって他者の優劣を判断することを見直してみてはどうだろうか。知的・技術的労働や事務・販売など仕事に従事する人びとは、ワイシャツ姿で働くイメージからホワイトカラーとよばれ、製造業・鉱業・建設業などの生産にかかわる仕事に従事する人びとは、作業服姿のイメージからブルーカラーとよばれるが、大学に通ったことがない人びとが相対的に多く、賃金も安価であるのはブルーカラーである。しかしながら、物を生産し、社会の維持に貢献しているのはブルーカラーの人びとであり、その人びとをなくして、われわれの社会は維持できない。だとすれば、学歴によって人びとの優劣を判断し、ある人びとの社会的敬意が損なわれることは健全ではなく、見直しが迫られる。その素地として、現在の高校教育が発足したときの理念に示されていたような、「ヨコ並び」の価値観が参考になるだろう。「ヨコ並び」といっても学びが同様であるわけではない。むしろ、さまざまな学びに対して多様な価値を認めていくこと、つまり価値の多元化によって、一元的な指標で人びとの相対的地位をタテに規定しない社会を創造することが可能となる。
つまるところ、学校に来る子どもたちはすでに多様であり、学校教育は子どもたちに違いをつくりだす装置であることを自覚することが、まずは肝要である。そしてまた学校教育は、自らがつくりだす違いをふり返り、その違いが問題にならない社会のあり方を考えるきっかけを生みだす力も秘めている。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
マイケル・サンデル『実力も運のうち──能力主義は正義か?』鬼澤忍訳、早川書房、2021年
小熊英二『日本社会のしくみ──雇用・教育・福祉の歴史社会学』講談社、2019年
門脇厚司・飯田浩之『高等学校の社会史──新制高校の〈予期せぬ帰結〉』東信堂、1992年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
津多成輔(つだ・せいすけ)
島根大学教育学部講師。筑波大学大学院3年制博士課程人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻修了。博士(教育学)。専門分野:教育社会学、共生社会学、進路研究、高等教育研究。
主要著作:
『教育社会学』共著、ミネルヴァ書房、2018年
「へき地校の教師が学力向上を重視する指導の論理」単著、『社会学年誌』第64号、2023年
「『共生社会』という言葉の認知と理想的な社会的配分の関連」単著、『共生学研究』第1号、2024年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)