他人と生きるための社会学キーワード|第2回(第2期)|ベスト・インタレスト──「会えない」日々が可視化したこと|麦倉泰子
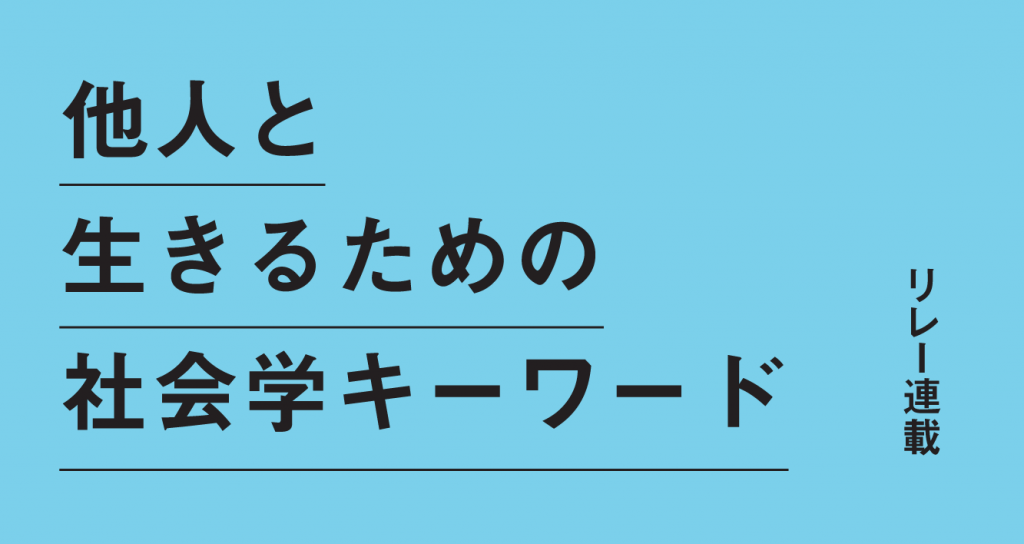
ベスト・インタレスト
「会えない」日々が可視化したこと
麦倉泰子
なかなか人と会えない、そんな日々が続いている。「会えない」ことによる影響を大きく受けているのが、障害のある人の支援の現場である。横浜市には、地域で暮らすさまざまな障害のある人の自宅を訪問したり、最寄りの相談室に足を運んでもらったりすることで、ゆるやかなつながりを維持するという少し変わった制度がある。顔なじみの支援者が、とくにこちらから連絡しなくても、いま差し迫った困りごとや緊急性がなくても、具体的な「サービス」を受けていなくても、「元気にしてる?」と定期的に来てくれるのだ。
ある相談室(制度上の呼称は支援室)を訪問したさいに、制度に携わるマネジャーが「自分にもこんな制度がほしいと思う」とぽろりと漏らしていたのが象徴的だ。親戚であっても年に一度、会えるかどうか。そして自明の前提として「コミュニティ」が存在するという時代がとうに過ぎたことはみなわかっていても、それに代わるオルタナティブを提案するところにはまだ至っていないというこの時代において、「顔なじみ」の人が、とくに連絡をしなくても定期的に来てくれることの安心感は大きい。
この制度の名前は「横浜市障害者後見的支援制度」という。「親亡き後の不安」を地域のネットワークによって支えていくシステムの構築をめざして、市独自事業として平成22年にスタートした。1か月から数か月に一度の訪問や面談によって、知的障害のある人、精神障害のある人などが住み慣れた地域で安心して暮らすことをめざす取り組みである。意図されているのは「親亡き後」の考え方の変化だ。家族が担っている多岐にわたるケアを社会的に分有するための試みということもできるだろう。本人のこれまでの人生やこれからの生活の希望、身体的な特徴、介護に必要な知識などについて、家族以外にも、継続的に見守る支援者たちを作っていくことがこの制度の目的である。
この制度では、各区に設置された後見的支援室の「あんしんマネジャー」とよばれる職員が、本人や家族と話し合って支援計画を作成し、見守りを開始する。後見的支援室所属の「あんしんサポーター」は数か月に一度、訪問や面談を行なう。継続的に顔を合わせていくなかで、本人のそれまでの生活史、これからの希望、いまの悩みや思いなどが、少しずつていねいに「記録」として蓄積されてゆく。こうしたゆるやかなつながりを保つことによって、いざ成年後見等が必要になったさいにも、見落とすことなく支援につなげていくことができるのだ。直接的なサービス提供は行なわないという制度の特性が、利害関係の少ないフラットな関係を築くことにつながっている。
面白いのは、地域住民に働きかけて見守りのネットワークを作ろうとしている点である。制度を知って共感した人たちがボランティアとして「あんしんキーパー」としての参加登録を行なう。障害のある人を支える実践をとおして、地域の紐帯が強くなる可能性があるのだ。
こうした制度が作られた背景にあるのは、意図的につながりを作っていかなければ網の目からこぼれ落ちてしまう人が出てきてしまう、という問題意識である。たとえば「8050問題」と呼ばれるように、高齢者の親が中年期の子どもをなんらかのかたちでケアしており、近所づきあいもないような場合、「こぼれ落ち」のリスクは高くなる。
つながりを維持するには、積み重ねられた信頼が必要だ。たとえば差し迫った困りごとはないものの、両親がいなくなったときに経済面・生活面で心配があるという本人の気持ちにどう応えるか。サポーターは、ご本人の好きなことが何か、ていねいに聞きとり、人となりをゆっくりと理解していく。サポーターの交代があっても、これまでの支援の内容がていねいに記された記録によって情報共有が確実に行なわれ、支援の継続性が確保される。制度利用のための周知の方法にも工夫が凝らされ、ご家族の近隣住民との関係を自然に利用しながら見守りを続けている。対人関係に不安を感じる方である場合、無理にあんしんキーパーとのマッチングを進めることはしない。その他のサービスを受けておらず、いざというときのセーフティーネットとして機能する可能性があるのはこの制度の訪問等のみ、という場合もある。
いずれにせよ、さまざまなかたちで積み重ねられたその人についての理解と信頼が、「いざというとき」に、その人にとっての「最善の利益」=「ベスト・インタレスト」を考える下地になっていくのである。
「ベスト・インタレスト」とは、認知症の人や、知的障害、精神障害のある人の権利擁護に関する議論のなかで、重要な原則として共有されている考え方である。日本では民法のなかに位置づけられている成年後見制度の運用に関して言及されることが多くなってきたが、もともとはイギリス意思能力法の実践の指針として示されているものである。
イギリス意思能力法においては、能力を欠く人のために、またはその人に代わってなされる行為や意思決定は、すべて本人の最善の利益のためになされなければならない、と定められている。日本の成年後見制度と異なる点は、日本の成年後見制度が家庭裁判所に認められた人のみによる後見事務を想定して設計されているのに対して、意思能力法は、対象者の範囲を限定せず、家族、有償の介護人、任意代理人、裁判所に任命された法定代理人、医療従事者に対しても同様に適用される点である。
ここで重要なのは、「ベスト・インタレスト」を考えるというのは、最後の手段である、という共通理解である。つねに優先されるのは、本人の自己決定であり、周囲の人たちは可能なかぎり、あらゆる手段を講じて本人の意思を確認しようとしなければならない。さまざまな可能性を試したうえで、本人に「特定の」判断ができないということが明らかになった場合にのみ、次の選択肢として「ベスト・インタレスト」を考える、という設計になっている。何が本人の最善の利益かを見出すことは容易ではないことを前提として、その人にとって何が最善かを考えることを重視する。横浜市の制度は、本人の意思決定に最大の価値を置きながら、その決定をするのが難しい場合にはそれを支える人びとの輪を作り上げていくことをめざしている。だから「後見的支援」という。
ところで「顔を合わせて話をする」という行為が根幹をなしているこの制度においては、直接「会えない」という今回の状況は、他者を理解するさいにわれわれが何を行なっているのかを可視化するという意味で、大きな意味があったようだ。現場では代わりに電話でやりとりをするなど苦心して工夫を凝らしていたが、やはり対面で話すよりは情報の量が減ってしまうというのが職員の方たちに共通した悩みだった。声のみのコミュニケーションでは、表情や声のトーン、「様子」(これには、服装や立ち居振る舞いも含まれる)がわからず、圧倒的に情報量が減ってしまうのだ。そして、これらの非言語的なコミュニケーションに、その人の「いま」を理解するための重要な情報が存在していることも多い。「会えない」という状況において、日ごろ私たちがコミュニケーションとしてとらえているものがいかに豊潤な内容を含んでいるものであるか、あらためて示した形となったといえよう。多くの人たちはコミュニケーションとは言語を介して行なわれるものであり、そこに本質があり、それ以外の情報は副次的だと考える傾向がある。「会えない日々」はコミュニケーションにおける私たちの言語/非言語のあいだの序列も明らかにしたといえるのではないか。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
新井誠「解題」『イギリス2005年意思能力法・行動指針』新井誠監訳・紺野包子訳、民事法研究会、2009年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
麦倉泰子(むぎくら・やすこ)
関東学院大学社会学部教授。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。専門分野:障害学、障害者福祉、福祉社会学。
主要著作:
『施設とは何か』生活書院、2019年
『支援の障害学に向けて』共著、現代書館、2007年
『共生と希望の教育学』共著、筑波大学出版会、2011年
『共生の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2016年
『パーソナルアシスタンス』共著、生活書院、2017年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)



