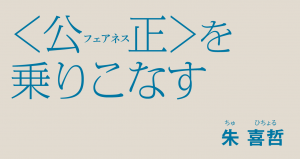他人と生きるための社会学キーワード|第3回(第2期)|大学との物理的距離──ユニバーサル・アクセスまでの隘路|津多成輔
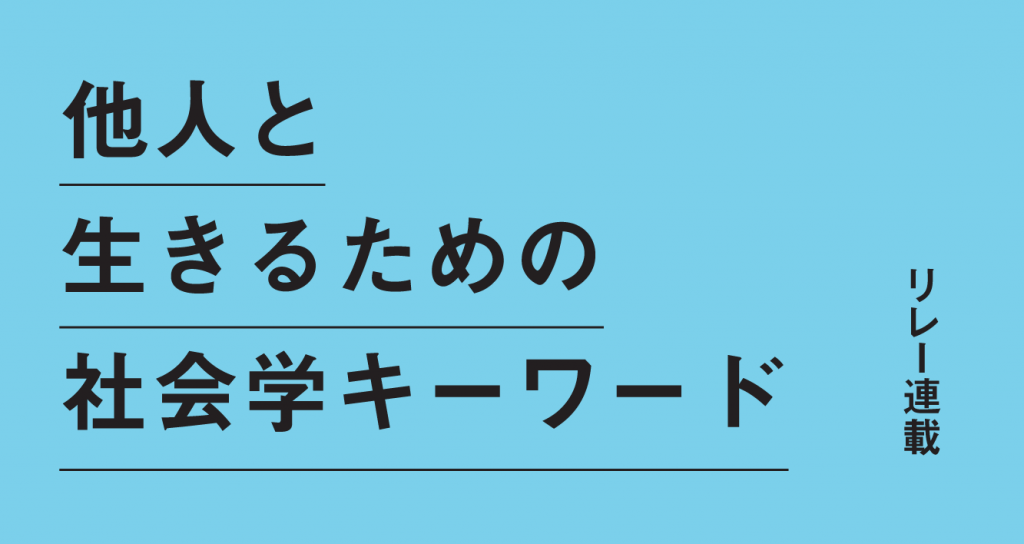
大学との物理的距離
ユニバーサル・アクセスまでの隘路
津多成輔
ある高校の先生によれば、「人のないところに大学をつくっても効率が悪い」らしい。たしかに、中央教育審議会が示した「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」でも、「規模の適正化」や「地域配置」という言葉を用いて18歳人口の減少をふまえた大学入学定員の抑制について言及されており、この先生の話は真っ当であるように思えるかもしれない。4年制大学(以下、大学という)が都市部に立地することは、われわれにとって当たりまえのような感覚であるが、大学の都市部集中の具体的な状況や大学教育に「距離」がある人びとについてはどれぐらいご存知だろうか。
2021年の日本の大学数は803校である。47都道府県で単純に割り算すれば、1県あたり約17校ということになるが、実際は東京都に143校で、半数以上が3大都市圏に立地する。他方、和歌山県や島根県など10県では5校以下だ。とくに和歌山県紀南地域では、少なくとも半径50kmに大学が存在しない。半径50kmとは首都圏の高速道路である圏央道の内側とほぼ同じ広さであり、東京駅からつくばや成田、木更津、鎌倉、八王子までの距離や、関西であれば大阪駅から京都や明石までの距離をイメージしていただけると、その広さを実感できるかもしれない。
この紀南地域の高校生は、大学を身近に感じることができない状況にある。私が実施した調査によれば、高校3年生の9割弱が大学生を見かけたり、大学生と話したりする機会がなく、半数以上が大学の敷地内に入ったこともない。このような大学との物理的距離は、大学との心理的距離に影響するだけではなく、経済的負担にもつながる。紀南地域からの大学進学には、一人暮らしの費用だけでなく、大学受験の時点から宿泊費や移動費等が必要となるため、4年間で少なく見積もっても自宅通学よりも数百万円程度大きな費用負担を強いられる。
このような状況にある紀南地域の子どもたちにとって、大学進学という選択肢は、身近に大学がある地域と比べて大きく制約されていることは想像に難くない。社会学では、このように特定の状況によって進路に一定の方向づけがなされ、その状況に身をおくと容易に脱出できないことを、陸上競技のトラックになぞらえて「トラッキング」と呼ぶが、大学との物理的距離は、心理的にも経済的にも、大学が少ない地域の子どもたちの進路をトラッキングしていることになる。このような状況は実際の大学進学率の差にもつながっており、大都市圏ではおおむね60%前後であるのに対して、地方圏の多くの地域では40~50%となっている。
ところで、いつから日本の大学は都市部に集中するようになったのだろうか。じつは、その歴史は戦前にまでさかのぼる。戦後すぐに設置された大学の前身は旧制大学や旧制専門学校が中心であるが、その多くがすでに東京都や京都府、大阪府といった地域に設置されていたことが、大学の都市部集中の背景にある。戦後の新制大学の設置にあたっては、従来の日本の強い国家統制に対して批判的なGHQが大学を地方に分散するように要請したこともあって、この都市部集中を解消しようとする動きはあった。結果として、すべての都道府県に国立大学が設置されるなどの一定の成果はみられたものの、その一方で半数以上の大学が3大都市圏に立地するなど、都市部集中に劇的な変化はみられなかった。それ以降は現在に至るまで、基本的には私立大学の増加が日本の大学教育の量的拡大を支えてきたが、都市部への新設校の抑制政策がとられた1970~80年代の一部の期間を除いて、大学の都市部集中の様相は強まりつづけている。このような歴史をふまえれば、地方-都市間の大学教育へのアクセスの差は、大学教育の大衆化とともに生じたものではなく、大学教育が選抜を経た限られた人びとしか享受できないエリート教育であったころから存在していたことがわかる。
一方で、2021年の日本の大学進学率は54.9%に達している。米国の社会学者であるマーチン・トロウは、進学率が50%を超えた社会では、高等教育がユニバーサル・アクセス段階(だれもが自らの選択により教育を受けることができる段階)に移行するという理念型を提示しているが、この見方にそえば日本の大学教育はユニバーサル・アクセス段階への転換期にあると考えることができる。トロウによれば、この段階における大学教育はかならずしもエリートのためのものではなく、すべての人びとに開かれ、多様化するとされる。実際に現在の日本の大学教育も、かつてのエリート教育ではなくなってきていることが肌感覚として実感できるのではないだろうか(「BF大学──大衆化した大学教育に求められるもの」を読んでみてほしい)。
じつは日本が批准する国際人権規約には、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること」と記載されており、だれもが高等教育にアクセスできることを保障する義務を負っている。とくに2012年まで留保されていた無償化について、当時の民主党政権が留保を撤回したことで、近年では高等教育就学支援が以前より充実しつつある。
このようにユニバーサル・アクセス段階への移行を目指すのであれば、冒頭で紹介した、人口の多い都市部に大学が集中することは当然だ、という考えには、少なくともつぎの2つの瑕疵があるように思われる。
まずひとつは、成績が優秀な人びとだけが大学に行くべきという考えについてである。われわれはしばしば、「早慶上智」「関関同立」「MARCH」など偏差値によって大学を序列化しがちであるが、ユニバーサル・アクセス段階においては、大学教育はエリートのための教育ではなく、現在の高校教育のようにすべての人にとって開かれたものになる。社会学では、学校教育には人びとを資質・能力に応じてそれぞれの社会的地位に振り分ける「選別・配分」の機能があるとされる。この「選別」の機能は、実際のところ日本社会において、人びとを偏差値によって序列化し「選抜」するものとなってしまっている部分がある。しかしながら、すべての人びとに開かれた大学教育への転換をはかるのであれば、縦に序列化するのではなく、「選別」の本来の意味するところである資質・能力によって選り分けるという点にたち戻って、いま一度そのあり方については問い直される必要があるだろう。とくに大学が少ない地域においては、進学率の低さもあって、大学教育がエリートのためのものであるという意識も根強いが、まずはこの意識から転換する必要がある。
もうひとつは、じつは人口比でみた場合でも、極端な大学教育機会の不均衡があることについてである。18歳人口に対する大学の入学定員は東京都で149.5%、京都府で152.3%である一方で、島根県では27.0%に過ぎない。仮に2040年まで現在の入学定員数を維持し、18歳人口の減少を加味した場合でも、島根県ではその割合は40.0%弱にとどまる。たしかに近年では、東京23区内の大学定員抑制政策の影響もあって、2021年の私立大学入学者数は、2016年と比較して、大学が多い地域(上位10都道府県)で1.0%減少し、逆に大学が少ない地域(下位10県)で7.8%増加している状況にある。その一方で、大学が少ない地域で入学定員の過半数を占める国公立大学入学者数は、大学が多い地域で1.0%、大学が少ない地域で1.3%減少していることもまた事実である。このような地方圏を含んだ国立大学の入学定員削減は、18歳人口の減少をふまえた大学の「規模の適正化」や「地域配置」といえるだろうか。
「大学全入時代」を自称し、ユニバーサル・アクセス段階への転換を志向するのであれば、私立大学による大学教育機会の拡大のみならず、地方圏で主要なセクターとなる国公立大学も定員の維持、あるいは拡大が望まれるのではないか。社会インフラとなる「大学教育」の実現には、われわれの認識の転換と地域間不均衡を解消する量的な整備が求められる。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
吉川徹『学歴社会のローカル・トラック──地方からの大学進学(新装版)』大阪大学出版会、2019年(初版:世界思想社、2001年)
天野郁夫『新制大学の時代──日本的高等教育像の模索』名古屋大学出版会、2019年
小川洋『地方大学再生──生き残る大学の条件』朝日新聞出版、2019年
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
津多成輔(つだ・せいすけ)
島根大学教育学部講師。筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻在学中。専門分野:教育社会学、共生社会学、進路研究、高等教育研究。
主要著作:
『教育社会学』共著、ミネルヴァ書房、2018年
「大学の都市部集中と大学進学機会」単著、『日本高校教育学会年報』第24号、2017年
「親の移動履歴・友人の居住地が高校生の進学希望地に及ぼす影響」単著、『共生教育学研究』第10巻、2022年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)