他人と生きるための社会学キーワード|第6回(第2期)|高校全員入学運動──「わがまま」を言うことの意味|池本紗良
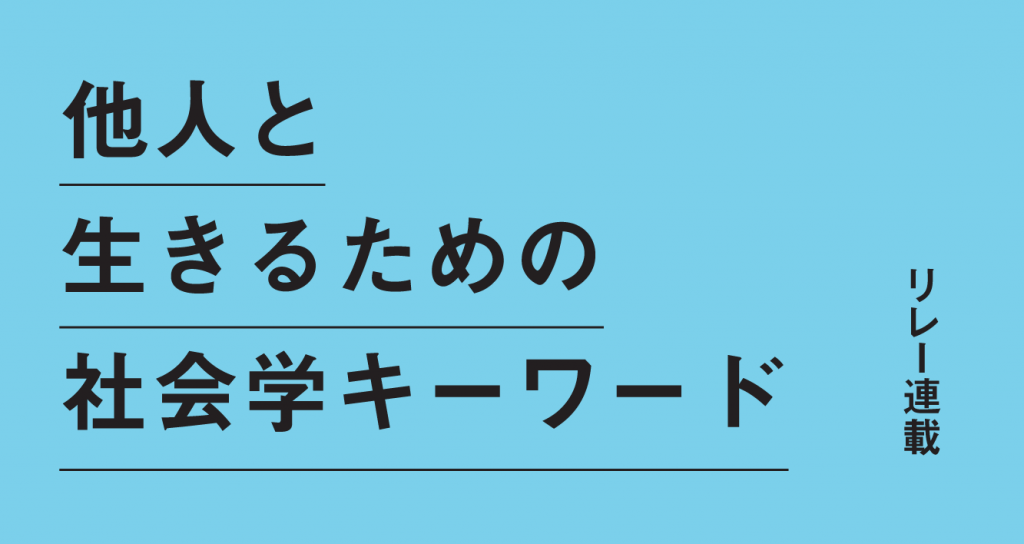
高校全員入学運動
「わがまま」を言うことの意味
池本紗良
いまや高校に進学することが「当たり前」になっている。むしろ進学するかどうかよりも、どの高校に行くかのほうに関心が向くであろう。だが、高校進学はかつて「当たり前」ではなかった。そして「当たり前」に高校に通えるいまの状態は、自然に整えられていったわけではない。
では、いかなるプロセスを経て高校進学が「当たり前」になっていったのか、その動きにいかなる意味があったのか。この振り返りをとおして、身近な不満から発せられた「わがまま」が、「当たり前」の社会システムの構築につながっていくことの可能性を考えてみたい。
高校進学が「当たり前」になっていくのは1960年代以降のことである。1960年代前半の高校進学率は約5割で、2人に1人ほどしか高校に行けなかった。そうした限られた者だけが通える高校を、希望するすべての者に開いていこうという取り組みとして「高校全員入学運動」(以降、高校全入運動)が展開された。この取り組みは、母親たちの「せめて子どもは高校へ」という声からはじまった。
この母親たちは、どこにでもいる市井の母親たちであった。ましてや当時の母親たちは、戦争によって満足な教育が受けられず、さらには女性というだけで教育は不要とされた時代に生まれたため、現在のように「当たり前」に高校に通うことができなかった女性であった。自分自身は高校に行くことがかなわなかったぶん、「せめて子どもは高校へ」といって高校増設を求めたのである。
この声が高校全入運動の推進力となった。この運動では高校三原則(小学区制・男女共学・総合制)の実現が具体的な目標とされた。通学区域を小さく設定すること(小学区制)、男女が平等に同じ高校に通えること(男女共学)、多様な教育課程を並置して課程間の序列をなくすこと(総合制)で、だれでも高校に行けるようにする制度づくりを要求したのである。
では、そのような運動がおこった当時、いったいどのような高校教育体制が敷かれていたのだろうか。じつは、文部省(当時)は1947年2月に「新学校制度実施準備の案内」を通知して以降、教育制度上は希望者すべてに高校入学を許可することを理念としていた。さらにはこの理念に則り、高校への進学には中学校からの報告書(いまでいう内申書のようなもの)だけが必要で、選抜のための学力検査は原則的には実施されないことを宣言していた。
だが現実的には、高校は選抜された者の教育の場だととらえられていた。たとえば、富山県の教育長は、「進学率の上昇で、全日制の高校教育を受けるのに適さない生徒がふえてきました。能力的には全く玉石混交の状態で、このままでは十分な教育効果は期待できません。全日制高校は、やはり選ばれたものの教育機関として、できるだけ各学校ごとにツブをそろえる必要があるのではないでしょうか」と語ったという(村松喬、1967、『教育の森⑦ “再編下”の高校』毎日新聞社)。また文部大臣も1965年12月、運動に参加した母親に対して、「現在の高校生は半数以上が能力がないというではないか。高校は能力のある者を入れるところだろう」と公言したという。希望者全入を打ちだしていたはずの教育行政側が、こうした認識を抱いていたというのは、刮目しておいてよいだろう。
この教育行政側の矛盾の背景には、第一次ベビーブームといわれる「団塊の世代」が高校進学を控えているという事態があった。急増する高校進学希望者に対して、いかに高校の席を準備するかが課題になっていたのである。そこで文部省は、1962年1月26日に閣議決定された「高等学校(公立)生徒急増対策」に沿って、高校進学率をなるべく抑えようという方針を採った。実際より低めに進学率を見積もって、高校新設を抑え、既存の学校・学級にできるだけ入れてしまうことで乗りきろうとした。
その結果、高校の現場では、音楽室などの特別教室を普通教室としたり、1クラスの収容を多くする「すしづめ学級」で対応したりすることになった。このころ、公立高校では1クラスに50~55名、私立高校では60~80名が収容されるところも多くあり、そうした教室の空気は満員電車なみの炭酸ガス濃度であったという(朝日新聞1964年12月7日朝刊)。通勤・通学の短時間なら我慢できるかもしれないが、その空間で勉強しなければならないと思うと、その過酷さが少しでも想像できるだろう。そうした空間にすらあぶれた生徒は、「中学浪人」として次年度の高校受験に備えることになった。1961年にはその数は約20万人いたという。
それでも高校新設を抑えようとした文部省は、高校全入運動の活性化を危惧し、1962年4月8日、「高等学校生徒急増対策と高校全入運動の可否」というパンフレットを各都道府県教育委員会に配布した。この文書のなかで、高校全入運動は「父兄の素朴な願いを政治的に利用する方便」であり「まともな運動ではない」と、批判をくり出した。そのうえで「高等学校教育を受けるに足る適格者を選んで、それに一定の内容を具備した教育を施す」ことを提唱した。この方針は「適格者主義」といわれる。「高校教育を受けるに足る能力」がある者のみが高校進学を許されるという方針である。
そしてこの適格者主義は、1963年8月に都道府県教育委員会に通達された「公立高等学校の入学者選抜について」にて制度化されていく。この通達によって、戦後廃止されたはずの入学者選抜の学力検査があらためて導入されることになった。高校は「当たり前」に通えるとは限らない、入学者選抜の出来・不出来によって振り分けられる場にされたのである。
こうした文部省の攻勢を受けて、高校全入運動は「まともな運動」であると弁明するために、とくに1963年以降、運動の「本質」を訴えていく。すなわちこの動きはけっして母親の「わがまま」ではなく、「高校教育を国民に解放し、人権と民主主義を守る国民運動」だと掲げられていった。
いっぽうで、この高尚ともいえる「本質」の掲揚について、ある母親はつぎのような言葉を残している。
「高校全入運動で話し合われたことは、本質をとらえずに高校運動をすすめている私たちにもよくわかりました。しかし“国民のひとりとして、ともに本質をふまえて全入をかちとらねば”といわれても、父母のみんなが、このことをつかむことはたいへんです。母親たちは、自分の子どもを高校に入れたいから運動に加わるのです。私自身もそうであり、そして当局や自民党に陳情をくりかえすなかで、教育行政者たちの教育に対する考え方がわかり、どのようにして予算がくまれていくのか、身をもって知りました。先生たちが討論された高い理論や意識も必要だと思います。しかし、より大切なのは父母にわからせてから行動させるのではなく、わからせるためにともに行動することだと思います」(小川利夫・伊ケ崎暁生、1971年、『戦後民主主義教育の思想と運動』青木書店)。
運動に加わるのに高尚な理念や知識はいらない、というのである。それよりも「自分の子どもを高校に入れたい」という「わがまま」を身近な要求として動きだす重要性が語られている。教育制度の中身や問題点をすべてわかっているから「行動」するのではなく、「行動」と同時進行でそれを「身をもって」知っていけばいい、とも読みとれるだろう。
これまで紹介してきた1960年代に展開された高校全入運動と現在の高校進学状況を照らしあわせて、この運動の意味を考えてみよう。
1960年代に導入が議論された入学者選抜は、現在ではさも当然のごとく実施されている。このことに鑑みると、高校全入運動が唱えた希望者全入は頓挫してしまったとみえる。小学区制・総合制を実現できなかったからだ。高校全入運動は高校間のランキング(序列)までは切り崩せなかったといえる。そのため、ランキング別に振り分けられる選抜システムは残りつづけ、いまでは当たり前の通過儀礼として受け入れられてすらいる。
だが、成功した面もある。それは男女共学をはじめとする、高校全入を達せられたことである。この運動がなければ、もしかしたら高校増設は進まず、だれでも通える場になることはかなわなかったかもしれない。このときだれも「わがまま」を言わなければ、文部省の計画にしたがって進学が抑制され、多くの者が高校に行けるような土壌が整えられなかっただろう。
そしてなにより、この動きを推進したのが、それまで発言権が限られていた女性たちであったということが重要である。この女性たちは、みずからの高校進学しかり、社会進出しかり、さまざまな面で制限されていた。高校について何の知識ももっていなかった女性が、ただたんに「自分の子どもを高校に入れたい」がために、文部省が決めた計画に異議を唱えていったのである。
この母親たちの動きが示しているのは、専門家のようなしっかりとした知識がなくても、人びとには身近な要求から社会を変えていく力があるということだ。そうした専門的な立場に置かれていない人びとからの要求は、すでに決められた社会制度に口を出す「わがまま」に見えるかもしれない。ましてや、かならずしもその要求が通るとはかぎらない。だが、自分たちの社会の問題を、自分たちで考えていくプロセスそのものに大きな意味があるということを、高校全入運動からはうかがい知れるだろう。
■ブックガイド──その先を知りたい人へ
富永京子『みんなの「わがまま」入門』左右社、2019年.
香川めい・児玉英靖・相澤真一『〈高卒当然社会〉の戦後史──誰でも高校に通える社会は維持できるのか』新曜社、2014年.
香川めい「高校教育の量的拡大と質的変容」『教育社会学事典』丸善出版、2018年、pp.400-401.
*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)
池本紗良(いけもと・さら)
早稲田大学文学部社会学コース助手・同大学院文学研究科社会学コース博士後期課程在学中。専門分野:教育社会学、共生社会学、ジェンダー論。
主要著作:
「国民統合装置としての『教育する母親』像の歴史的検討──バーンスティンのコード理論を手掛かりに」単著、『共生教育学研究』第6号、2019年
「『教育ママ』言説における母親像の変容──1962-1980年の『読売新聞』を事例に」単著、『ソシオロジカル・ペーパーズ』第30号、2021年
「高度経済成長期における女性の公共性の様相──高校全員入学運動に活用された『母親』カテゴリーに注目して」単著、『社会学年誌』第62号、2021年
![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)

